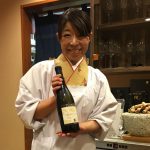やっぱりクラスメイトが・・・
しばらくぶりに記事を書いてみる気になった。
と言うのも、ある講座で一緒になったクラスメイトがWINE-WHAT!? 主催のセミナーに出るというので、行ってみることにしたからだ。今回のお題は「冷涼VS温暖、ルクセンブルクとベツレヘムの比較テイスティング」。
うむ~う、恥ずかしながら、どちらの産地も今まで全くご縁がなかった。ルクセンブルクは、私がJSAワインエキスパートを取得した2016年、日本ソムリエ協会の教本に「国別一人当たりの年間ワイン消費量」が世界一の国として紹介されていたので、その点だけは鮮明に覚えている。
「あんな小さな国がなんでトップなの?」と疑問に思ったものだ。しかも、当時の教本にはルクセンブルクについての説明ページはなかった。翌年の教本に初めて登場するのだが、2019年の最新版ですら3ページちょっとしか説明がない。気になって、OIV(国際ブドウ・ブドウ酒機構)の2018年のデータを調べてみたら、現在はポルトガルがトップになっていて、ルクセンブルクはトップ20にも入っていない! なぜ? 私にとっては全く“謎の国”なのである。
そしてベツレヘム。ところで、どこにあるんだっけ?
どうやらパレスチナ自治区にあるらしい。もちろん教本にはそのページが載っていようはずもない。つまり、私にとっては大いにマニアックな産地同士の対決なのである。
対決はブラインドで
セミナーのナビゲーターは、WINE-WHAT!? の鈴木文彦代表取締役。初めてお目にかかれて、ちょっと感激である。
まずは、冷涼気候を代表してルクセンブルクから。
インポーターの今野有子氏(株式会社アルムンド代表取締役)から説明。ルクセンブルクは、東西にドイツとベルギー、南はフランスという位置関係。面積は神奈川県と同じくらいだ。
ワインの産地は、東側のドイツと国境を隔てているモーゼル川沿いの約42㎞。
モーゼルと聞くとすぐにドイツを思い浮かべてしまうが、こちらも同様に川沿いの急斜面にブドウ畑がある。斜度は40%を超えるところもあるそうだ。
平均標高は150~200m。ブドウの栽培農家は340軒、ワイナリーは60軒。
ルクセンブルク全体の生産量のうち、白が90%で圧倒的に多く、赤とロゼが10%。スパークリングワインは全体の25%だそうだ(クレマン・ド・ルクセンブルクが有名)。
温暖気候の代表は、パレスチナ自治区のベツレヘムのワイン。
実に興味深い。鈴木さんの説明を補足する形で、インポーターの峰岸喜美子氏(株式会社ザ・セイクリッド・ワイン代表取締役)が登壇。
とあるワインスクールで、辛く、厳しい半年間の講座を一緒にやり遂げた私のクラスメイトだ。いつもエナジーにあふれた女性である。
なんと! パレスチナ自治区のあるイスラエルは、5,000年以上に及ぶワイン造りの歴史があるという。なるほど、キリスト教の聖地は「ワインの聖地」でもあったという訳だ。
7世紀に一度ワイン造りが途絶えたが、1800年代後半にロスチャイルド家がフランスからブドウ樹を輸入し、その後、1980年代にエドモンド・ド・ロスチャイルド男爵の支援によって、コーシャーワインのワイナリー「カーメル」が設立されて、復興を果たしたとされる。現在はゴラン高原を中心に、主に国際品種が栽培されている。「ヤルデン」の名をご存知の方も多いだろう。
イスラエルのアリエル大学の研究者によると、かつてパレスチナには約120種類の土着品種があり、そのうち20品種が実際にワインに使われていた可能性があるという。クレミザン修道院ワイナリーでは、キリストが生まれたときに飲んでいたワインを再現しようと、2008年から土着品種のみでワインを造っている。ちなみにミサでは白ワインを使っているそうだ。これは、ワインをこぼしても神父の衣装に染みがつかないようにとの配慮から。パレスチナではローマンカトリックのパレスチナ人が、自家消費用にワインを造っているとのことだ。
ワインのラベルには、キリストの手から放たれた鳩の絵が描かれていて面白い。そして、セミナーのお土産にいただいたオリーブオイルもクレミザン修道院ワイナリーで造られていて、そのラベルにはオリーブの枝をくわえた鳩が描かれている。
これで、ひとつの物語になっているのだ。なるほど、芸が細かい。
テイスティングはブラインドで、ルクセンブルクとベツレヘムでトータル4種類(白2、赤2)を比較試飲した。順番にご紹介する。
①ハムダニージャンダリ2017/クレミザン修道院ワイナリー
(ベツレヘム 白)
聖地ベツレヘムのサレジオ修道会・クレミザン修道院ワイナリーで醸造。ハムダニもジャンダリも土着のブドウ品種の名前。いずれも50%ずつ使っている。果皮は黄色がかったグリーン。主にベツレヘムとヘブロン地域で栽培されている。
淡いレモンイエロー。グリーンなノート。レモン、グレープフルーツといった柑橘系の香り。酸味が高く、心地よいほろ苦味。土壌のカルシウム分がワインにも感じられる。生の米のような香りもわずかにあって、ミュスカデを思い起こさせる。
ブラインドでは、冷涼な気候で造られたのかと思ってしまった。アルコール度数は11.5%。3,800円(税抜き)。
②リースリング2016/ドメーヌ・ヴァンモーゼル
(ルクセンブルク 白)
ルクセンブルク最大の協同組合(240軒の栽培農家が加盟し、4つの醸造所を所有)で醸造。淡いレモンイエロー。酸味が高く、すっきりしているが、日当たりの良さを反映してか、まろやかな口当たり、ふくよかなイメージ。ハチミツ、洋ナシ。
アルコール感やや強め。温度が上がってくると、少しペトロール香。冷涼な産地にしては、熟度が高いように感じた。試食として提供されたスイス伝統のじゃがいも料理「ロスティ」にも合う。5,000円(税抜き)。
③バラディ2015/クレミザン修道院ワイナリー
(ベツレヘム 赤)
バラディも土着品種。アラビア語で「我が国」、「その土地の固有」を意味する。
ベツレヘム近郊のクレミザンの丘で栽培。標高885mという場所柄、昼夜の寒暖差が大きく、ブドウは酸味を保持したまま完熟する。
淡いラズベリー・レッド。薄っすら黒みがかっている。ラズベリーやレッドチェリーといった赤系果実の香り。ふんわりと樽のニュアンス(古樽を使用)。ピノ・ノワールだと思ってしまった。
アルコール度数は13%。3,800円(税抜き)。
④ピノ・ノワール2016/ドメーヌ・ヴァンモーゼル
(ルクセンブルク 赤)
ルクセンブルクを代表する詩人であり、劇作家、作曲家としても活躍したエドモンド・ド・ラ・フォンテーヌの名を冠するワイン。
淡い、まさにイチゴ色。薄っすらオレンジのニュアンスも見て取れる。少しキャンディ香。すでに干しプラムや干しイチジク、なめし皮の香りも。とにかく酸味が高い。CO₂が残存しているのかと思うような、チリチリとした口当たり。タンニンは比較的多く、樽由来のスパイスも感じられる(新樽を使用)。6,000円(税抜き)。
今回は、緯度や大きなくくりでの気候では「冷涼VS温暖」と言いつつも、どちらにも共通していたのは、日照量の豊富さによるブドウの熟度と標高の高さからくる酸の高さによって、バランスの取れたエレガントなワインに仕上がっていたということだ。近年、食の変化に合わせて、ワインもよりエレガントなスタイルがトレンドになっている。素材を活かしたライトでヘルシーな料理が好まれることから、それに伴って、繊細な風味を邪魔しない、エレガント系ワインが求められているのだ。その点から見ても、いずれのワインも消費者ニーズやトレンドを踏まえた造りになっているのは流石といったところだ。
ワインあるところご縁あり
ブドウもワインも、この世の中には星の数ほどある。短い人の一生においては、出会えるブドウやワインはほんの一握りだ。そう考えると、今回、ルクセンブルクとベツレヘムという、どちらかというとかなりマニアックなワインを試飲できたのは、まさに“神のお導き”といったところだろう。これも素晴らしいご縁である。
ちなみに、クレミザン修道院ワイナリーには「ベツレヘムの星」という名のついたワインもあるそうで、この星はキリスト誕生の瞬間に大きな光を放ち、東方の三賢者がこれに導かれて、幼子イエスのもとを訪れたとされている。かつて多くの画家がモチーフにしてきた宗教画のテーマ、いわゆる「東方三博士の礼拝」のお話だ。なるほど、ここでも私の好きなもの同士がつながっているということか。
私は常々、「ワインと美術」には似ている部分があると思っている。いずれ、このテーマで書いてみるつもりだ。ちなみに、クリスマスツリーのてっぺんに飾られる大きな星が「ベツレヘムの星」である。
最後に、冒頭の「ルクセンブルクの謎」に戻る。
なぜ、一人当たりの年間ワイン消費量が世界一だとされていたのかというと・・・。どうやら国境を越えてルクセンブルクに仕事や買い物に来ている人たちのワイン消費量を含めてのカウントだったということらしい。東京都のワイン消費量が、他県に比べて多いのと同じ考え方だ。その後、統計の取り方が見直されたようだ。まあ、そんな訳でワインにまつわるさまざまなデータも日々変わり続けていることを考えると、常に最新の情報をチェックする姿勢が大いに大事なことだと実感する。
だから皆さん、日々、マニアックなワインも積極的に飲んで、大いに知見を深めること、そして教本は「ためらわずに毎年購入する」ことをオススメする(笑)
ルクセンブルクとベツレヘムのワイン、ぜひ一度お試しあれ!
<試飲したワインの情報>
○ルクセンブルクのワイン
「ここだけワイン」 kokodakewine.com
○ベツレヘムのワイン
「ザ・セイクリッド・ワイン」 https://www.sacred-wine.net