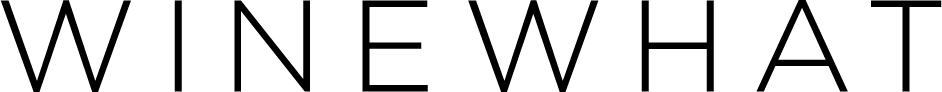ワイン界のドンたちが目指したもの
まずは応接室で、ワインメーカー兼畑の責任者であるマイケル(Michael Silacci)から、オーパスの歴史について説明を受けます。
豪華な応接室(この写真は以前訪問したときに撮ったもの)
オーパスは、アメリカとフランスのワイン界の重鎮、ロバート・モンダヴィ氏とロートシルトのフィリップ氏が共同で創立したブランドです。実はこのお二人、ひとりは「長く共にビジネスをするのだから、まずはお互いをよく知り、友人となるのが先決だ」、もうひとりは「一緒に仕事をしてみないと、本当の友人になれるかどうかは分からない」というスタンス。この違いのため、オーパス・ワンとして始動・開始するまでに長い時間がかかったそうです。
でも、ワインに対する熱い想いは二人とも同じ。「カリフォルニアでボルドースタイルの最高傑作をつくる」という理念のもと、1979年にオーパス・ワンが誕生したのです。そして、ご存じのとおり、二人の巨匠たちたちの傑作は、カリフォルニアワインの普及に大きく貢献することとなったのです。
2001年からオーパスに関わっているマイケルも、この創業者たちの想いを受け継いでいます。
ワイン造りは光合成?
「植物は光合成をするのに主に赤と青の光を使っている」
と理科の時間で習いましたよね!(わたしの記憶ボックスからは完全に消えていましたが…)オーパス・ワンのワイン造りにも、なくてはならない2つの光があるそうなのです。
マイケルいわく
「ワイン造りを光合成にたとえて説明するのが好きなんですよ。ぶどうの樹たちにとって赤と青、2種類の光が大切なように、私たちにとっても赤と青の重要な要素があります。赤はパッション、青はリーズン(理由)です。ワイン造りに対する情熱はもちろんですが、それだけではダメ。“どうしてそれをするのか”という理由を冷静に分析し、明確にすることが大切なのです」とのこと。
畑に移動。ぶどう栽培についても教えてもらいました。
マイケルとナタリーから畑についての説明を受けているところ
オーパスには、ワイナリー周辺の畑も含め、4ヵ所の自社畑があり、広さは全部で70ヘクタール弱ほど。ぶどうの種類の割合は、78%がカベルネ・ソーヴィニヨン、6.5%メルロー、6.5%カベルネ・フラン、数パーセントのマルベックとプティ・ヴェルドーが植えられているとのこと。
オーパスの畑は栽培密度が高いことで有名です。樹と樹の間隔を狭め、思うように根が張れないような環境にすると、ぶどうたちは危機感から、競い合うように深く根を張るようになり、小粒で風味が凝縮した果実を生みます。また、肥沃な土壌のところでは、あまり大きく育たない種類を使用するなど、土壌に合ったクローンや台木を選ぶことも大切にしているとのことでした。
これから春から夏にかけてはぶどうの樹たちがどんどん成長する季節。
でも、そのまま放置するわけにはいきません。幹から伸びてくる不要な茎や多すぎる葉っぱは取り除かれ、伸びすぎた茎はカットされます。葉っぱが多すぎると、通気が悪く病気にかかりやすくなったり、後々フルーツに十分光が当たらなかったりします。また不要な茎があると、そちらに栄養が取られ、果実に栄養が充分にいきわたらないことも。そのためぶどうの樹は収穫間近まで、ていねいに管理されます。しかもそのほとんどの作業が手作業なのです! ワインの価格にはこういった作業コストも含まれているのです。
管理の行き届いた畑
さあ次はワイナリーの中の見学です。
ワイナリー内部。床に空いているこの穴は…
この床の丸いもの、何だかわかりますか?
実はこれ、発酵用のタンクです。正確に言うと、見えているのはタンク上部です。収穫されたぶどうは選別された後、このタンクに移されるのです。下の階にタンクを置くことでぶどうの移動が簡単にできるようになっているのですね。圧巻はぶどうの除茎や選別をするこの機械。
最新の機械でクオリティの高いぶどうだけを選別します
ぶどう以外の葉っぱやゴミ等がどんどん取り除かれていくシステムです。またニコンのレンズが全てのぶどう粒をスキャンし、目的とする大きさや色に満たない果実たちは容赦なくはじかれるように設定されているとのこと。全ての粒って…考えただけでめまいがしますね。テクノロジーの発達はすごい!
巨大なタンクがずらりとならびます
全てのタンクにおなじみのロゴが!
そして最後は…ついにお待ちかねの試飲です!
美しく並べられたグラスたち。さすがオーパス、安定のおいしさです
この豪華なバレルルームを見ながら、ワインメーカーと一緒にテイスティングできるのはまた格別ですね。現行ヴィンテージの2013年は、とても出来の良い年といわれていて、周囲の評判も高いです。
以前訪問して試飲した際には、濃いベリーの香りが全面にでていたのですが、今回は少しホコリっぽさが加わっていました。ワインは瓶の中でもどんどん変化していくのですね。
バレルルーム。現在、バレルに入っているのは2014・2015・2016年のヴィンテージ。新樽の中で約18ヶ月、ゆっくりと熟成されます
オーパスからとどいたDM。「2016年ヴィンテージは今のところとんでもなく良いできですよ!」とのことです
去年はテイスティングの授業でオーパス・ワンのバックヴィンテージを試飲する機会があり、2005年の美しさに感激したのを覚えています。できることなら2013年ヴィンテージも、10年後、20年後に飲んでみたいものです。
おいそれとは手が出ない、足も運べない高級ワイナリーを、こうやって特別待遇でいろいろ見られて、質問までできるって、幸せだなあ、と酔いしれながら後にしたのでした。
裏側からみたオーパス