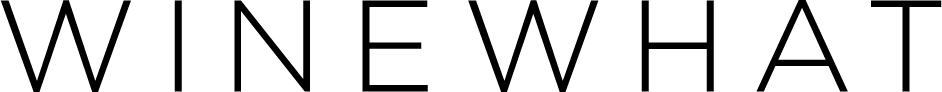「ルイ・ロデレール・ブリュット・ナチュール・フィリップ・スタルクモデル」と「ルイ・ロデレール・ブリュット・ナチュール・ロゼ フィリップ・スタルクモデル」。価格はいずれも15,000円(税別)。パッケージ&ラベルデザインはフィリップ・スタルクによる
クリスタルだけではもったいない
1776年設立の老舗シャンパーニュメゾン、ルイ・ロデレール。1876年、ロシア皇帝アレクサンドル2世の要望から誕生した「クリスタル」は、高級シャンパーニュの代名詞として広く知られている。いや、むしろ、クリスタルは知っているけれど、それを造っているのがルイ・ロデレールということを知らない人もいるかもしれない。そしてそうであればもったいない。
ルイ・ロデレールはイギリスやフランスのワインのプロに非常に評価が高いシャンパーニュメゾンだ。スタンダードキュヴェの「ブリュット・プルミエ」は、飲んでみれば価格対品質で傑出したシャンパーニュだと納得できるとおもう。スタンダードキュヴェはメゾンの顔。最高級シャンパーニュ「クリスタル」の造り手によるスタンダード、という緊張感がある。
「クリスタル」から「ブリュット・プルミエ」まで、緻密なワイン造りを徹底するルイ・ロデレールは、経営でいえば、200ha以上の自社畑をもつ、シャンパーニュのなかではかなりの大手メゾンながら、一族による家族経営を貫いている。その畑は、ピノ・ノワールならモンターニュ・ド・ランス、ムニエはヴァレ・ド・ラ・マルヌ、シャルドネはコート・デ・ブランと、適地適作。そして、それらの自社畑の大半でビオ・ディナミ農法を実践している。「テロワールを表現するため」と、栽培・醸造の両方の責任者であり、ルイ・ロデレールのスポークスパーソンともいうべきジャン・バティスト・レカイヨンは言うのだけれど、そういう農業をやっているメゾンならではのシャンパーニュが「ブリュット・ナチュール」だ。
このたび、レカイヨンが引っさげて来日した、「ルイ・ロデレール ブリュット・ナチュール・ロゼ フィリップ・スタルク」という、「ブリュット・ナチュール」の初のロゼとともに、ここでは、レカイヨンから聞いた、ブリュット・ナチュールの話を紹介したい。
自然派シャンパーニュ
ブリュット・ナチュールはルイ・ロデレールの社長 フレデリック・ルゾーとレカイヨン、そして、フランスのデザイナー フィリップ・スタルクとの会話からスタートしたという。誠実で、ミニマルで、ダイアゴナルで、モダンなシャンパーニュ、という抽象的な概念が会話のなかで描き出されて、これをレカイヨンが解いた。日照に恵まれた年、粘土質の土壌で育ったブドウで造るフレッシュなシャンパーニュがそれであろう、と。そして、会話から数えて10年以上たって、このシャンパーニュはブリュット・ナチュールという名で2006年ヴィンテージをもって2014年に世にあらわれた。
建築、インテリアのデザインが多いけれど、文房具や家具など、デザインするものは多岐にわたるフィリップ・スタルク。とはいえ、もちろん、ワインの造り手ではない。ワインは、しかし、彼のアドバイスも受けて、大きくいえばノンドザージュのヴィンテージシャンパーニュ、となった。
「フィリップ・スタルクとの会話は、シャンパーニュとはなにかを問い直す経験になった。あるいは、本物とはなにか。本質への問いは、歴史を紐解く作業でもあり、シャンパーニュはどこにいくべきか、未来を問うものでもあった」
ジャン・バティスト・レカイヨン
レカイヨンはそう言う。そうして、ブリュット・ナチュールは極めて飾り気のない造り方へと至った。
畑はアイ村の西、マルヌ川を挟んでエペルネの対岸、キュミエールにある。南を向いたマルヌ川を望む丘だ。面積10ha、農法はビオ・ディナミ。収穫は一日で行われ、ブドウはいっしょに搾汁される。区画ごと、とか、品種ごと、とかに分けない。これは昔、実践されていた造り方だそうだ。だから品種ごとの割合は厳密には出せないけれど、だいたい、ピノ・ノワールが55%、ムニエ25%、シャルドネ20%となる。
マルヌ川の丘の斜面に広がる粘土質土壌。キュミエールは黄色く塗られたところにある
「酵母は天然酵母。ドザージュはしない。マロラクティック発酵もしない。SO2(酸化防止に使われる亜硫酸)も最小限。私が知る限り、シャンパーニュでノンドザージュ、ノンマロラクティックのシャンパーニュはほかにはない」
「私達はヒッピーみたいな格好をしているわけではないけれど、これは自然派ワインと言っていいとおもいます。とはいえ、自然派ワインを造るのが目的ではない。シャンパーニュの本質への問いへの答えとして、テロワールの表現を突き詰めたのがブリュット・ナチュールです」
もちろん、これだけナチュラルであれば、途中でワインをダメにしてしまわないように、さまざまな技術が必要になる。ドザージュによる取り繕い、などは、そもそもルイ・ロデレールのレベルであればしないだろうけれど、ノンドザージュであれば、ドザージュでの微調整すら望めない。ブドウと醸造で勝負する。好ましくない菌が入ろうものなら、すぐにダメになってしまうのは、自然派ワイン同様。細心の注意が要る。しかもこれは長期熟成させるヴィンテージシャンパーニュだ。
酸化への耐性も低いから、果汁と空気の接触はなるべく避けたい。発酵槽において二酸化炭素を利用し、最後の打栓の際にコルクとワインの表面との間に残る空気を押し出すジェッティングという手法を採用した。こういった技術は、クリスタルにも一部、反映されている。
また、天然の酸化防止剤としての機能もある酵母についても、レカイヨンの興味はより強いものになったそうだ。今回の来日では、とある有名な日本酒の酒蔵の見学にもいったそうだ。
「教科書的にいえば、イーストが果汁のなかの糖分を食べて、アルコールとガスを出す。そのイーストは最終的には一種類が残ります。けれども、それは酸やアルコールに耐性のあるイーストが最終的に生き残るだけで、途中には数々の、最後まで生き残るわけではないイーストがいるのです。その存在が、最終的なワインの味わいに無関係だとは私にはおもえません。テロワールの表現にあたって、野生の酵母を使いたいのは、そのためです。酵母の状態をモニターしていると、実にざまざまなものが活動する。人工培養された酵母を入れるのでは、それはできない。たしかに、培養された酵母も、そもそもはテロワールからとられたものかもしれません。しかしそれは、1960年代、70年代から、安全な環境で育てられている。いま現在、環境中で生きているものとは違うとおもいます」
2006年ヴィンテージではじまったブリュット・ナチュールは、2009年ヴィンテージ、2012年ヴィンテージと造られ、2012年ヴィンテージでは初めて、ロゼが造られた。これは、やはりフレデリック・ルゾーとレカイヨン、そしてフィリップ・スタルクとの会話がきっかけだ。スタルクが「グレーは美しい色で、グレーのワインは造れないのか」と語ったとき、うっすらとしたロゼ色のシャンパーニュであれば造れる、とレカイヨンが応じたところからスタートした。
造り方は白のブリュット・ナチュールの5日前にピノ・ノワールを収穫して赤ワインを造り、それを白とまぜる、というもの。全体に対して25%が赤ワインとなる。ピノ・ノワールの抽出ではアルコール発酵前に、低温でブドウを寝かして抽出をする、コールド・マセレーションを行っている。
「最初は、ロゼをノンドザージュで造るのは無理だろうとおもっていました。わずかでも加糖しないと、酸のエッジ、タンニンをきつく感じるとおもったのです」
ところが、そういうことにはならなかった。同じ2012年のブリュットのロゼと比べると、明らかに軽快で爽やか。タンニンはあるのかもしれないけれど、むしろうま味のような味わいを感じ、酸味は確かに強いけれど、きついというのではなく活き活きとしている。これと比べると、「ブリュット・ヴィンテージ・ロゼ」は、がっちりとした骨格の重たいワインにすら感じるほどだ。

ブリュット・ナチュールの全3ヴィンテージ
同じことは、白のブリュット・ナチュールにも言える。スタンダードキュヴェのブリュット・プルミエが、スタンダードながらに、フレッシュさと熟成のうま味とをバランス良く表現し、シチュエーションを選ばない、アペリティフでも食事に合わせても問題のないシャンパーニュで、クリスタルが時間を惜しまず注ぎ込んだ濃密なシャンパーニュの経験ならば、ブリュット・ナチュールは青空のように明るく、快活だ。
今回は、ブリュット・ナチュールについては2006年、2009年、2012年とすべてのヴィンテージを試すことができた。つまり、ブリュット・ナチュールのヴィンテージシャンパーニュとしての側面も体験できた。
最新の2012年は傑出した年で、さらにピノ・ノワールの年だった、という。
「南向きの斜面ゆえの太陽のフルーティーさ。ひんやりとした土のニュアンス。濃厚で、凝縮し、エネルギーがある。2012年は7月の中旬くらいまでは湿った年だった。春の霜で生産量は低かった。しかしそれ以降はドライで素晴らしい夏。生き延びたブドウはよく太陽の恵を受けました」
2012年だから、決して若いとはいえない。もう7年も前だ。しかし、若々しい。これと比較すればぐっと落ち着くのが2009年。レカイヨンは、ドライで、クリスピー、さらにタニックだ、とまで言う、渋みがある。同時に筆者はすこしクッキーのような香りを感じた。味わいも2012年よりも甘みを感じる。
2006年になると、もしかしたら醸造時に使用されている樽の影響もあるのかもしれないけれど、木のようなニュアンスをより感じる。2012年と2009年が6年なのにたいして、2006年だけ、8年間、殿とともに熟成していることも関係があるかもしれない。口に含めばとろりとまろやかで、なめらかだ。これは熟成によるところも大きいだろう。
レカイヨンは夏が暑く、ブドウがよく熟した2006年は、太陽を感じさせ、ジャミーでメタリックだ、という。
2006年はルイ・ロデレールのセラーにもごく僅かにしか残っておらず、今回は日本で輸入元のエノテカがごく僅かにもっていたもの。3ヴィンテージをそろえて試飲できる機会は、もう、めったにあるものでもないだろう。ただ、まだ熟成する可能性がある。そして、熟成してもなお、ノンドザージュのシャンパーニュとして、活き活きと、溌剌としているけれど、さて、では、熟成することがよいことか。2012年に戻ってみて、それはそれで、また魅力的だ。甲乙つけがたい。
「ブリュット・ナチュールがどれほど熟成に耐えるのかは、私にもわかりません。2006年はまだ、熟成する。けれど、今後、いつ、どうなるのかは、実際に飲んでみないことには、わからないのです」
さらに、ブリュット・ナチュールはリアクティブなワインだ、ともいう。
「サーブする温度やグラスによって、専門家でも違うワインだ、と感じるほどに変化します」
繊細なブリュット・ナチュールを、レカイヨンはハーブティーにもたとえた。
この、削ぎ落とされたピュアなワインの追求の道は、いまやスティルワイン、コトー・シャンプノワへも向かっている。行き着く先のひとつは、スティルワインだ、という。
「それはブルゴーニュのワインのようなものではなく、シャンパーニュのチョーク質の土壌を表現したもの。であれば、オークはあまり合わない。シャンパーニュの土壌で育ったブドウには少し脂っぽい印象がある。むしろ、アンフォラ、コンクリートタンクをステンレスタンクとともに使っていくことになる」
構想はかなり具体的だ。コトー・シャンプノワにはシャンパーニュのナチュラルワイン、という呼び方もある。この場合のナチュラルは発泡していない、という意味だけれど、ルイ・ロデレールのそれは、このブリュット・ナチュールと同様の意味で、ナチュラルなワインになるだろう。
ルイ・ロデレールの将来を楽しみにしながら、ブリュット・ナチュールをセラーに入れておきたくなった筆者だった。
左から、2012年 ルイ・ロデレール ブリュット・ヴィンテージ・ロゼ、2012年 ルイ・ロデレール・ブリュット・ナチュール・ロゼ フィリップ・スタルクモデル、2012年 ルイ・ロデレール・ブリュット・ナチュール・フィリップ・スタルクモデル、同2009年、同2006年、そしてルイ・ロデレール ブリュット・プルミエ