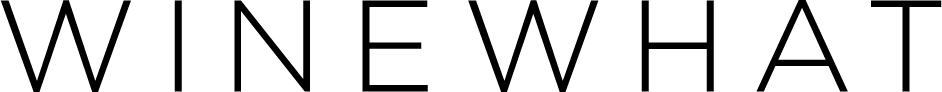真ん中がトニーさん。右奥が岩田さん。
創業1853年。ブドウの平均樹齢50年
主催したのは、オーストラリア、ニュージーランドを中心とするワインの輸入・販売を行なっているGRN株式会社。同社はここ10年連続2桁増の売り上げを記録、好調な業績を背景に、今まで以上に業界に積極的にアピールしていくという。ベルギーで開催された「ソムリエ世界大会2019」日本代表の岩田渉氏とコンサルタント契約を結んでもいる。
この日のセミナーの主役は、南オーストラリア州のバロッサ・ヴァレーでブドウを栽培するカレスキー家の7代目当主トニー・カレスキー氏。
カレスキー・ファミリーは1838年にプロイセン、いまのポーランドあたりからバロッサ・ヴァレーにやってきた。南オーストラリア州で移民が始まったのは1836年なので、パイオニア的な存在だ。農場を開いたのは1853年で、ブドウ栽培のほか、家畜を含む作物を先祖代々育てている。
栽培したブドウは、100年以上にわたってオーストラリアのビッグネーム、ペンフォールズに供給してきたけれど、せっかくいいブドウがあるのだから、ということで2002年にワイナリーを設立、ワイン造りに乗り出した。トニーさんは三兄弟の長男で、三男が醸造、次男が栽培を担当している。
本拠地は、南オーストラリアの州都アデレードからクルマで1時間ほど北に行ったバロッサ・バレーの北西部に位置しているグリーノック地区。ここはちょっと標高が高くて涼しいエリアで、赤ワインの生産に向いている。
バロッサには13のサブリージョンがある。それぞれが異なる土壌と異なる気候を持っているので、バラエティ豊かなワインができる(岩田氏によると、バロッサではとりわけ土壌に注目されており、サブリージョンを土壌で特徴づける「バロッサ・グラウンド・プロジェクト」なる調査活動も進められている)。
典型的なテラロッサ(赤土)とライムストーン(石灰岩)土壌のグリーノック地区。果実味豊かなワインを生む。緩やかに傾斜した畑が特徴。
アイアンストーンに浅い砂地の土壌で、旨味のあるワインを生み出すモッパ地区の畑。手摘み中。
カレスキーのブドウ畑は、グリーノックから4〜5km北のモッパ地区にもある。粘土質土壌のグリーノックでは果実味豊かなワインができるのに対して、アイアンストーン(鉄鉱石)の土壌のモッパでは鉄由来の旨味のあるワインができあがる。
ブドウ畑は50ヘクタール。東京ドーム10コ分の広さで、樹齢2~3年の赤ちゃんから1875年に植樹した樹齢144年の老ブドウの木まで、幅広く栽培している。平均樹齢は50年というから、極めて古い畑だ。
ワイン造りはオーガニック & ビオディナミ
ワイン造りはすべてオーガニック、もしくはビオディナミの認証を取っている。
「(カレスキーのワイン造りの)キーは、バランスです。よい品質のワインは、よい品質のブドウがないとできない。ビオディナミの手法で養分の高い健康的な土壌を育てて、ブドウを栽培し、それをワインにしている。それが秘訣です」とトニーさん。
ワイン・メイキングはナチュラルなつくりを心がけており、天然酵母を用いて発酵を行なっている。畑の個性をしっかり出すことが第一で、タンニンを添加したりはしない。
「畑由来の味わいがカレスキー・ワインの特徴です。清澄、ろ過も一切やっていません。ワインからなにかを取り除くようなことはしない。動物由来の清澄剤も使っていませんので、昨今流行りのビーガン・フレンドリーなワインです」
ビーガンというと、イギリス人プロレスラーで「サブミッション・マスター」の異名をもつザック・セイバー・ジュニアが有名だが、知らないひとは知らないでしょうから、それはさておき、ベジタリアンよりも厳格な菜食主義者で、動物から搾取しないことをモットーにするひとたちのことである。岩田さんはトニーさんの言葉を受けて、ソムリエ的視点からこうまとめた。
「オーストリア、欧米ではビーガンのかたは想像以上に多い。ラベルにビーガンの認証が貼ってあるカレスキーのワインは日本でもインバウンドのお客さまのことを考えると、間違いなく必要になってくるカテゴリーです」
それから岩田氏は次のような質問をした。
「バロッサ・シラーズというと、リッチで、濃縮感があって、いわゆる“ビッグなワイン”というイメージが強い。そうしたビッグ・ワインへの反動から、ここ最近、ボルドーやカリフォルニアでも、より繊細かつピュアで、エレガントなものを求める傾向がある。カレスキーは2002年にワイン造りを始めたということですけれど、これまでにスタイルを変えたことはありますか?」
トニーさん答えて曰く、「いいえ、同じです。非常にトラディショナルな方法を使っています。収穫も、熟しぎてジャミーにならないように、バランスを心がけてやっています。非常にシンプルなワイン造りです」
以上のような前振りのあと、いよいよカレスキーを代表する5種類の赤ワインのテイスティングとなった。
トニーさんがまずそのワインについて解説し、そのあと岩田さんがさらに説明を加える、という形式でセミナーは進んだ。
テイスティング開始
左端から1〜5。
1. Kalleske Clarry’s GSM 2017
クラリーズ GSM 2017
グルナッシュ60%、シラーズ30%、マタロ10%。グルナッシュは1940年代に植えられた。3つの品種のフレッシュな果実味を保つために古樽で5カ月熟成、熟成後ブレンド。非常にフローラルなニュアンスがある。参考上代4,000円
岩田 外観は明るいルビー色で透明感すら感じられる。香りの第一印象は、豊かなフルーツの香り。レッドプラムやラズベリーなどの、皮がピンと張り詰めているような新鮮さ、ジューシー。グルナッシュ由来のパフュームのような華やかなニュアンス、シラーズがもたらす独特の、食欲をそそるような香り。
飲んでみて最初に感じるのは、ピュアなジューシーさ。フルーツのまっすぐな、何もお化粧していないような、飲みやすさ。ブドウ品種のそれぞれのよさを生かした、絶妙なブレンド。シラーズがもたらす味わいの複雑味、深み、それを支えてくれる非常にきめ細かいタンニン。飲みやすさと同時に、満足感をもたらす。合わせるお食事にも汎用性がある。軽やかさも同時に見受けられ、バロッサ・シラーズというと、ビッグでパワフルなイメージが強いわけですが、こういったスタイルのワインが造られていることを知ってほしい。
2. Kalleske Zeitgeist Shiraz 2018
ツヴァイガイスト シラーズ 2018
1905年から1994年までに植樹されたシラーズ、10種類をブレンド。除梗あと、オープントップの発酵槽で自然発酵。1日2回攪拌。SO2(亜硫酸塩)無添加。6月の早い時期にその年のヴィンテージの特徴を損なうことなくボトリング。新しい試みで、オークでの熟成はしていない。「ツヴァイガイスト」は輸入元による命名。参考上代4,000円
岩田 SO2無添加で、ハンズオフであるにもかかわらず、これほどコントロールされているのはブドウの質の高さ、ワイン・メイキングの質の高さによるもの。香りは、ブラックベリーやブルーベリー、青黒い果実のニュアンス。味わいは、より充実感がある。伸びやかな酸味がワインに活力を与えていて、口中でエネルギーを感じさせさえする。生き生きとしたシラーズのよさが前面に出ている。トニー、2018年のバロッサのヴィンテージのキャラクターについて教えてください。
トニー 2018年はパーフェクトな年になりました。2016年はちょっと寒くてエレガントなイメージですが、バロッサは非常にコンディションが一定で、ブドウの栽培に向いている。
カレスキーの強みは100%自社畑だということ。いいタイミングだと思えばすぐに収穫できます。
3. Kalleske Moppa Shiraz 2016
モッパ シラーズ 2016
モッパは昔、金鉱があった地区。粘土質に浅い砂地の土壌。シラーズにヴィオニエ3%、プチヴェルド7%をブレンド。ヴィオニエはアロマチックさを、プチベルドは長期熟成に向くタンニンをワインに与える。15カ月。300リッターの大樽で熟成。参考上代4,300円
岩田 モッパと、このあとのグリーノック、このふたつを比較すると、サブリージョンを語る魅力が感じられると思う。こちらはヴィオニエ、プチヴェルドをブレンドしているから、そこはグリーノック シラーズと大きく違うが、それ以上にそれぞれの産地の個性が表れている。モッパの方がよりエレガント・サイドにある。非常に熟した黒い果実、ブラックベリーやブラックチェリーは同じでも、決定的に違うのはスパイスやセイボリーと言われるような食欲を伴う香りがある。スパイスといってもカレーに使われるようなエキゾチックなスパイスだったり、独特なスモーキーさや、土っぽいミネラルのような、色々な要素を持ち合わせている。
味わいは、洗練された酸味が液中にしっかり溶け込んでいる。プチベルド由来のグリップの効いたタンニンが強固なストラクチャーを感じさせて、飲みごたえがある。次のワインと飲み比べてみると、サブリージョンの違いを理解する上で、触感の違いとなって現れているので、ぜひ意識して欲しい。
4. Kalleske Greenock Shiraz 2016
グリーノック シラーズ 2016
グリーノックの単一畑のシラーズ100%。土壌は典型的なテラロッサ(赤土)とライムストーン(石灰岩)。緩やかに傾斜した畑ゆえに上から下へと3~5段階で収穫する。収穫時期の違いがワインに複雑さをもたらす。参考上代5,600円
岩田 香りの第一印象は、よりフルーツの豊かさが前面に出ている。それでいながら、スパイスやお花やその他の香りがたくさん感じられる。スパイスだけに焦点を当てると、モッパの方がよりグリップが効いたドライ・スパイスのような印象で、グリーノックの方が暖かさに由来する、バニラ、チョウジ、リコリスなど甘さを思わせるスパイスがより増えている。そこに、アメリカン・オーク由来のココナッツ的な甘さが融合されている。
飲んでみると、3、4番目のワインとも共通するシラーズのブドウのよさが、よりナチュラルで、インテグレードされた酸が味わいのスタイルを決めている。タンニンに注目すると、ココアパウダーのような細かいタンニン、チューニング・キャンディを噛むような、チューイーなタンニンを作っている。カチッとしたモッパに対して、グリーノックは、口中、横に豊かにより広がっていく滑らかさがある。ワイン・メイキングを多少変えてはいるけれど、人為介入を抑えて、ブドウとテロワールをしっかり表現できるような造りになっている。
5. Kalleske Johan Georg Shiraz 2015
ヨハン・ゲオーグ シラーズ 2015
1875年に植えた樹齢144年のブドウによる100%シラーズ。収穫量をきわめて低く抑えている。1エーカーあたり、1トン、1本の木で2kgのブドウの収穫。土壌はグレーの粘土質で、石英を豊富に含む。何層にも、複雑に感じられる旗艦ワイン。長いフィニッシュ。参考上代20,000円
岩田 (カレスキーの畑のブドウが使われていた)「ペンフォールズ グランジ」は1本10万円。同じようなクオリティがこの価格で味わえる。樹齢144年というのは国宝級の古木だから、
もっとプロモーションで使いましょう。非常に長い余韻はダイレクトにブドウの質の高さを表している。最高級のワインに共通する、凝縮感がありながら、驚くべき軽やかさをも持ち合わせている。充実感、凝縮感、力強さと同時に、繊細さも味わえる。気がつけば、ボトル1本飲んでしまっているタイプの軽やかさ。バロッサ・ヴァレーのシラーに、こういう緻密でナチュラルなハーモニーのあるワインがあることを知って欲しい。

最後に記者の個人的な感想を記すと、テイスティングに供されたワインはいずれも美味だったけれど、最後のヨハン・ゲオーグはとりわけ美味で、グラスをすっかり空けて飲んでしまった。だって、おいしいんだもん。総じて、カレスキーのバロッサ・シラーズは舌がピリリとするようなスパイシーさ(とりわけモッパ シラーズ)と軽やかさ、それに混じり気のないピュアさが感じられた。
ジャンシス・ロビンソンMWの『ワインの飲み方、選び方』(新潮社)によれば、バロッサ・シラーズといえば、「南オーストラリアやヴィクトリア産のもっと濃厚なものは、チョコレートの香味」があって、「どれも、比較的甘く、アルコール分が高」いというイメージだった。同書は日本での初版が1998年、コピーライトは1983年。前述のごとく、カレスキーがワイン造りを始めたのは2002年である。
カレスキーを知って、自然派バロッサ・シラーズを知ることになったセミナーでした。

カレスキーのブドウの平均樹齢は50年!