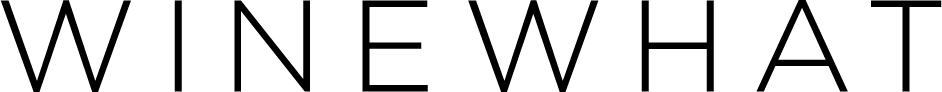ピエール・ド・ブノワさん
ブーズロンのアリゴテは苦味を語る
ドメーヌ・ド・ヴィレーヌはブルゴーニュの有名なドメーヌ、ロマネ・コンティの共同経営者、オベール・ド・ヴィレーヌが1971年に設立した。ブーズロンのアリゴテがAOCを名乗れるようにした立役者でもある。ピエール・ド・ブノワさんはその甥にあたる。
まず、醸造施設を見せてもらったのだけれど、巨大な木樽とピカピカの直方体のステンレスタンクが目を引く。
「上の階でプレスされた果汁がこの大樽に入ります。畑の大きさに応じて樽はサイズがちがいます。マロラクティック発酵後、バトナージュはせず、澱とともに10〜12カ月熟成させます。このとき、樽のなかで液体は自然に8の字を描いて対流します」
タンクの形状や材質は、アンフォラも卵型のタンクも、あらゆるタンクを試して、結局、木製の大樽が一番、空気と触れる面積が少なくて、アリゴテにあっている、という結論に至ったそうだ。
「澱引き後、ガスは抗酸化のために使えるので残したまま、タンクでアッサンブラージュ。そのあとボトリングです」
ステンレスタンクは特注品。ピカピカなのは香水造りなどに使われる高級なステンレスだからだそうだ。形状が浅くて四角いのは、液体の表面積を増やしてガスが抜けやすいようにするためだそう。
「ワインにはなるべく触れません。かつては仕事が多かった。それはリスクがあったからです。私のおじいさんの時代は、畑はボルドー液に含まれる銅で青く見えたし、早めに収穫してきて、一生懸命絞って、バトナージュして、とたくさん仕事をするのが普通でした。しかしそれは過去の話。現代の知見をもってすれば、わずかなボルドー液で、オーガニック栽培の、きちんと熟したブドウを育てられる。であれば、なるべくブドウに任せればいい。人間はちょっとお手伝いをするだけです」
樽の置かれているカーヴの素材はコンクリート。ピエールさんによると、交差リヴのヴォールトのようなデザインは、ロマネスク様式だという。
樽熟成のカーヴは醸造所のすぐ奥。寸法は黄金比にしているという
「コンクリートを造るときにはブーズロンの水を使って、ワインの澱を混ぜました。そうすることで、コンクリートがワインのために使われるとわかる、とおもうのです」
筆者、そういう話は好きだ。農業におけるアニミズムはポエジーだ。
ここまで聞いたあと、ワインを試飲させてもらう。
代表格はもちろん、ブーズロンのアリゴテ。さらに、ブーズロンの畑で栽培されているシャルドネとリュリィのアリゴテ、ブーズロン、メルキュレイ、リュリィそれぞれの畑のピノ・ノワールも試した。
左から二番目がブーズロンのピノ・ノワール。フルーティーでやさしいタンニン
「ブーズロンでは、一つの畑にアリゴテ、シャルドネ、ピノ・ノワールを植えるのが伝統です。石灰の多い丘の上にアリゴテ、粘土質の増える中腹にシャルドネです」
アリゴテはやはり際立っていた。ピーンと強い酸だけれど、さわやかで美しい。瑞々しくもあり、骨格もある。水のようであり、ワインのようでもある。
「19世紀、ブーズロンのアリゴテは、高級品でした。フィロキセラの後、丘の低いところに植えられて、樹勢の強さから量産品種のような扱いをされて偉大さを失ったんです。いま、ふたたび丘のうえでアリゴテを育て、アリゴテは復権しています。強いエネルギーをもった品種ですから、小さい樽でしめつけてはいけない。酸化還元作用をゆっくりとすすめると、ふくよかになります。ゆっくり熟成することをワインが学ぶんです。温暖化も、アリゴテの復権を後押ししています。アリゴテは酸味があって、清涼感を保ちやすいからです。また、ブドウの果皮が厚く、皮に由来する苦みがあります。日照が強くなったことは理由のひとつだとおもうのですが、シャルドネにもその傾向がみえます。この苦みは、タンニンとはちがうものですが好ましいもの。私の祖父は、良いワインのサインだと言っていました。この苦みの表現は、将来、酸味に代わる表現になるとおもいます」
確かに、苦みを感じます。この正体ってなんなのでしょうか。
「ブルゴーニュがもともとは海の底だったことを考えれば、表現すべきテロワールのひとつは海底だ、といえるかもしれません。ここのワインからはどれも塩気を感じます。苦みの正体、成分を私は知りませんが、うまみ、のようなものだと感じています」
苦みを語る時代がくるのか。なんだかワクワクする話だった。