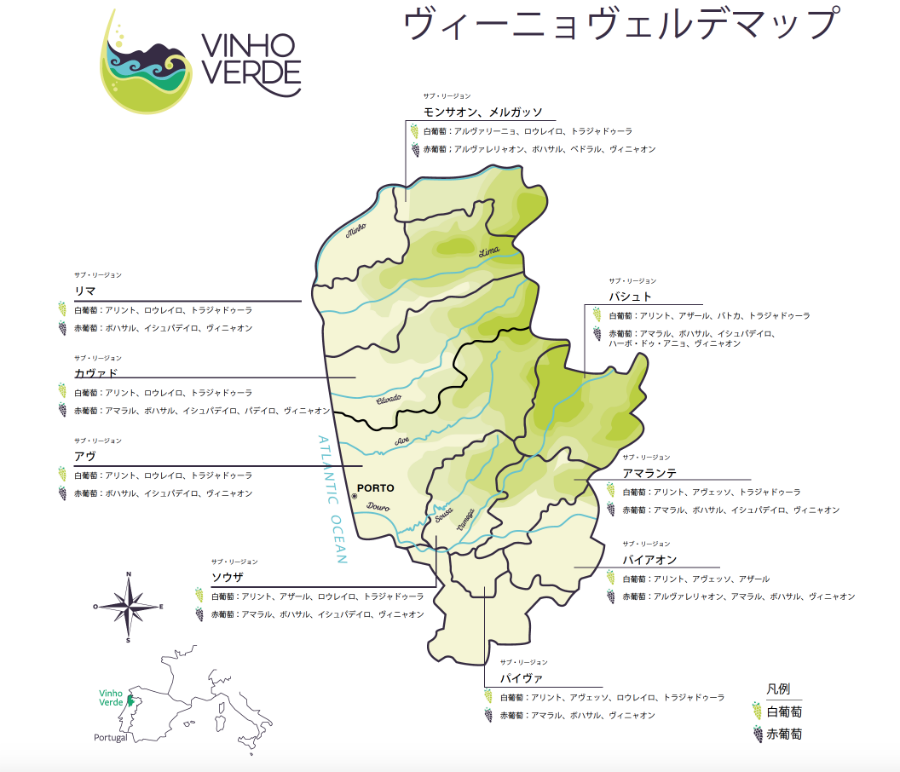試飲は「クルヴォス」というラインが中心。
テイスティングは9種類
話をテイスティングに戻すと、キンタ・デ・クルヴォスは製品の種類が豊富で、少なくともテイスティング用に9種類出てきた。
最初は「クルヴォス・スペリオール」。レモンにトロピカル・フルーツの香り、フレッシュで若々しくていきいきしている、というクラシックなスタイルのヴィーニョ・ヴェルデの白である。ロウレイロ75%、トラジャドゥーラ15%、アリント10%のブレンドで、これまで飲んだヴィーニョ・ヴェルデのなかでは辛口、ドライだ。アルコールは11.5度と軽めなのは同じだけれど、糖はたった1.5g/dm3、酸は6g/dm3とフツウのレベルで、炭酸ガスは少しだけ加えてある。「グルメの料理に合う」とミゲルさんは言う。
次に、「クルヴォス・ロウレイロ」がグラスに注がれた。ロウレイロは前述したようにこの地域でよく育つから、ふんだんに使える。それなら、100%ロウレイロで「ナチュラルなフレーバーを楽しみたい」ということで、つくられた単一品種のヴィーニョ・ヴェルデである。スペリオールよりも柔らかでフルーティで、炭酸ガスが入っていない。アルコール12度、糖5.5g/dm3、酸5.8g/dm3である。
3本目は「クルヴォス・アルヴァリーニョ」。アルヴァリーニョ100%であることはもちろん、8〜12時間クイック・マセレーションを行なっている。アルコール度13度と高めで、糖6g/dm3、酸5.5g/dm3。2本目のロウレイロよりもいっそうフルーツを思わせるところがアルヴァリーニョの特徴だ。ちなみにアルヴァリーニョはひとつのブドウの房が小さくて量がとれないためコストが高い。
単一品種シリーズは続き、4本目は「クルヴォス・アヴェッソ」。アヴェッソは栽培に時間と手間がかかるからブドウ生産者もつくりたがらないし、売りたがらない、ということをミゲルさんは何気なく語った。しかも、わざわざドウロ渓谷の終わりのバイアオンというサブ・リージョンから運んでいる、ということも淡々と語った。
あまりに淡々と語っておられるので、それがどういう意味なのかよくわかっていなかった。
アヴェッソはキンタ・デ・クルヴォスが属しているサブ・リージョンの「カヴァド」では栽培していないのだ!
自分ちの小地区(サブ・リージョン)の外から持って来たアヴェッソ100%のこれをテイスティングするや、「おお、アヴェッソ! この香り!」と感嘆の声をあげたのは、今回のプレスツアーのCVRVVの担当者で添乗員のゴンちゃんことTomás Gonçalvesさんだった。「より複雑で、クリーミーで、アップル、ドライフルーツの味わい」とミゲルさんは淡々と表現した。
アヴェッソ100%のこれは、糖と酸はそれぞれ6g/dm3、酸5.5g/dm3だけれど、アルコールは13度と高めで、なにより炭酸ガスを入れておらず、フツウの白ワインに近い味わいで、ヴィーニョ・ヴェルデの可能性の広がりというものを感じさせた。
5本目に、アヴェッソ60%、ロウレイロ40%のブレンド「コルヘイタ・セレシオナダ(COLHEITA SELECIONADA=選択された作物)2017」がグラスに注がれた。「すごくいい結果がでた。ほかのメーカーでこのコンビネーションを出しているところはない。ウチのオリジナルだ」とミゲルさんは淡々とジマンした。しかも、フランス産のオーク樽で熟成させている! ヴィーニョ・ヴェルデって熟成させないのが特徴だと思っていたら、そういうルールが決められているわけではないらしい。アヴェッソ100%と同様、糖6g/dm3、酸5.6g/dm3はフツウながら、アルコール度数は13度ある。フルボディでストラクチャーがしっかりしていて、複雑、というのもミゲルさんのジマンだ。

どれがどれやら、この写真ではわかりませんが、雰囲気はこんな感じ。詳細はこちらを。
6本目はロゼで、イシュパデイロ100%。アルコール度は11.5度、糖は9g/dm3、酸は7.5g/dm3と、糖と酸が多めで、甘口のロゼらしいロゼだった。「サラダやシーフードに合わせてよいし、アペリティフにもどうぞ」とミゲルさんは言った。
7本目の「レゼルヴァ 2015」は、果実を選んだアヴェッソ100%でつくったワインをフレンチ・オークの樽で1年寝かしたヴィーニョ・ヴェルデ。これこそ、わずか2日とはいえ、それまで培った筆者のヴィーニョ・ヴェルデ感を覆す味わいだった。だって、これはもうニガい。ヴィーニョ・ヴェルデなのに複雑みがある。3400本しかつくっていない貴重品でもある。アルコール度は13度と高めで、糖と酸はそれぞれ3g/dm3と6g/dm3で、4本目のアヴェッソ100%より低めになっている。
8本目は待ってましたのスパークリング、「クルヴォス・レゼルヴァ」。アリント70%、アヴェッソ30%で、アリントはスパークリングに向くということだけれど、ここでもアヴェッソが活躍している。シャンパーニュの伝統的つくり方で2年熟成させていて、2500本しかつくれない。最初の年は1000本のみだったそうで、人気に量が追いついていない。泡が強めで、酸味があってドライで、スカッとする。例の3つの数値は、12.5度、6.5g/dm3、そして8.6g/dm3である。
ラストの9本目は「アフェクトゥス(afectus=「愛情」)」というシリーズの「アーリー・ハーヴェスト」という2017年収穫のブドウを使った甘口の微発泡だった。アペリティフかデザート用につくられたこれは3回目のヴィンテージを迎えたばかり。
この種のものとしてはこの地域で初めてで、ロウレイロ90%、トラジャドゥーラ10%の、ミゲルさんいわく「ベスト・ペアリング」からなる。
アルコールは9度と軽めで、糖は35g/dm3もある。ここんちのロゼの4倍! でも酸が7g/dm3としっかりあるせいだろう、甘さがあとを引くことはない。
というように、キンタ・デ・クルヴォスにはヴィーニョ・ヴェルデのクラシックなブレンドから単一品種、熟成モノ、スパークリングに加えて、甘口まである。同じ白でも、それぞれに明確な個性を与えることによって、ヴィーニョ・ヴェルデの質をより複雑なものへと進化させていこう、という意思が明瞭に感じられたのだった。

ファミリー・ビジネスのキンタ・デ・クルヴォス2代目のミゲルさん。
あなたは改革派なんですね、と念のためにミゲルさんにたずねると、「新しいことにチャレンジしていきたい」と淡々と答えた。
試飲後、カニや小エビがどっさり出てきた。海が近い証拠だ。それらをサカナにキンタ・デ・クルヴォスのヴィーニョ・ヴェルデをいただいた。全員お腹いっぱいになると、小型バスに乗り込み、心地よい眠りにつきながら今宵の宿へと向かった。

カニは万国共通でひとを無口にする。茹でただけで小細工なし。日本人の口にも合う。

特産のプリプリの小エビ。満足感を得るには熟練皮むき職人になる必要がある。

食後のデザートはフルーツ。シンプルの極み。贅沢だなぁ。
つづく