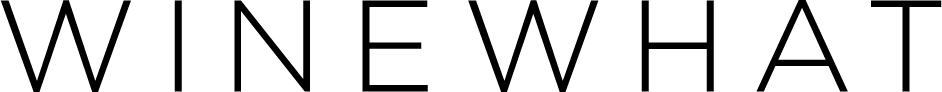青春のワインとよびたい
ヴィーニョ・ヴェルデといえば、ときに10%を下回る低いアルコール度数とさわやかな味わいに、わずかな発泡があるワインだ。
産地はポルトガル。ポルトガルは、スペインがあるイベリア半島の、西側。北と東はスペインに接し、西は大西洋に接する。ヴィーニョ・ヴェルデは、そのポルトガルの北西部、おもにミーニョ地方で造られるワイン。ヴィーニョ・ヴェルデの産地は、ワインから転じてヴィーニョ・ヴェルデ地域ともよばれる。なにせ、現在、約2万ヘクタールのブドウ畑は、DOCとしては世界でも最大級の規模なうえに、原産地の境界の設定は、はやくも1908年になされているからだ。ワイン造り自体も紀元前96年から51年の文献に言及があるそうで、少なく見積もっても2200年の歴史があるという。
さて、ヴィーニョ・ヴェルデが訳すとヴィーニョがワインで、ヴェルデが緑、緑のワインとなることは、もはやここで繰り返すまでもないだろう。ただ、それはもちろん、ワインが緑色だというのではない。赤でも白でもロゼでもオレンジでも、ヴィーニョ・ヴェルデになりうる。
ヴェルデには、いくつかの意味が込められているようだ。そのうちで、ヴィーニョ・ヴェルデを理解する上で役に立ちそうなのは、まず、若い、という意味。日本では若いことを青いという。青春という言葉があるように。ヴィーニョ・ヴェルデのヴェルデは、その青に近い意味を持ち、若いことを意味する。若くないワインはヴィーニョ・マドウロという。ブドウは早摘み、熟成もあまりしないで、さっさと飲む。そういうワインは溌剌として若々しい。あるいは甘酸っぱいかもしれない。ワインが青春まっただなかなのだ。
そして、もうひとつ、産地が青々としていること。ヴィーニョ・ヴェルデ地域の降雨量は年間平均1,200mmで、これは日本でいえば、勝沼などと近い数字。勝沼は夏から秋にかけて雨が降り、ヴィーニョ・ヴェルデ地域では10月から4月と、冬に雨が多い。というちがいがあるけれど、ワインの産地としては、日本同様、雨量が多く、水が豊かだ。気温の変化はそう大きくなく、日照もしっかりとあり、となれば結果、産地は青々としている。ポルトガルは相続で土地が分割されてゆくので、農家は小規模で、ブドウと一緒に、他の作物を育てたり、畜産をやったりしている。それでいよいよ、青い。
垣根栽培だけではなく棚もある。農地の内側で飼料用コーンなどを育て外縁部にてブドウを育てる、というのも伝統的な農業
大雑把な言い方だけれど、水や光に恵まれていると(土壌はおもに花崗岩なので痩せている)、ブドウの果実は凝縮しにくい。ポルトガル市場は赤ワインが好きで、ヴィーニョ・ヴェルデ地域も実は50年ほど前までは、生産量の半分以上は赤ワインだったという。ただ、どうしても、産地の特性上、濃密で骨格のしっかりした赤ワインを生み出すのは苦手だ。
それで白ワインが主流になって、いまや生産量の80%以上が白。のこりを赤とロゼでわけあっている。
この方向性は現在、うまくいっている。10年ほどで販売量は倍以上に伸びた。年間6000万リットルの販売量うちの、およそ、45%を輸出している。国内にのこった55%にしても、最近はアメリカのセレブが家を買ったりして、人気急上昇中のポルトガル。ワインツーリズムも盛んで、外国人がポルトガルに来て飲んでいる分も、無視できないようだ。
価格が安く、アルコールは弱く、さわやかで、飲みやすい。それに、青いイメージ。これが時代にあって、ヴィーニョ・ヴェルデは世界的に波にのっている。クリーンでデザイン性に富んだボトルが多いのも、成功の理由にあるかもしれない。ジャケ買いしても、失敗はするまい。
と、ここまではWINE-WHAT!?の各所でも、すでに述べたような内容で、今回は、まだ、前段である。
青年は大人になる
青春真っ盛りのヴィーニョ・ヴェルデは、販売量も伸びているけれど、販売額はもっと伸びている。それはつまり、ワインが高級化しているということだ。何が起きているのか。ここが、今回の話題。
今回の7本。詳細は後述します。クールでスタイリッシュなデザインは、ピシっとしていて、ラテン的な開放感とはまたちがう、真面目なお国柄を感じます。裏ラベルには、ワインの説明が、わかりやすく書かれているものがほとんど。各ワイナリーのホームページも、整然としていて使いやすく、デザイン性も高いと、やはり真面目です
これを解説してくれたのが、東京は、虎ノ門に本店を構える人気のワイン専門店、カーヴドリラックスの別府 岳則さん。各方面のエキスパート揃いのカーヴドリラックスで、別府さんは、ポルトガルワインについては、ポルトガルでも認められる専門家だ。その別府さんによれば、ヴィーニョ・ヴェルデは、いまや、単にさわやかで若々しいだけのワインではないのだ。
赤坂見附のワインと和食の料理店、「酒亭茜坂」を舞台に、ヴィーニョ・ヴェルデ協会 日本オフィスが主催した、和食とヴィーニョ・ヴェルデを楽しむというプレス向けの夕食の席で、別府さんの解説とともに、実際に7種類のヴィーニョ・ヴェルデが飲めたのだけれど、このときのワインのことを紹介しながら、ヴィーニョ・ヴェルデのいまを紹介してみたい。
まず1本目。
Casa de Vila NovaというワイナリーのVINHO VERDEというストレートな名前のヴィーニョ・ヴェルデ。最初ということもあって、いわゆるヴィーニョ・ヴェルデで、品種は土着品種のブレンドである。具体的にはロウレイロ、アリント、アヴェッソがブレンドされている。微発泡のさわやかなワインで、ブドウの果実の香りが心地よい。
ところで、このワイナリー、ホームページを見ると、今回のワインでブレンドされていた、ロウレイロ、アヴェッソ、アルバリーニョ、それぞれの品種を単一で使ったワイン、さらに、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブランと国際品種を単一で使ったワイン、さらには、アヴェッソ100%のリザーブという、フレンチオーク樽で12ヶ月熟成したワインをラインアップしているではないか。
これである。ヴィーニョ・ヴェルデではいま、単一品種、ヴィンテージ、樽熟成、そして炭酸ガスを加えない、という、より一般的なワインにちかいワインが造られているのだ。
そこで2本目。
Quinta da Lixaという造り手の、ロウレイロ。その名の通り、ロウレイロというブドウを100%使用している。ヴィーニョ・ヴェルデ地域の海沿いのエリアでひろく育てられているロウレイロは、ヴィーニョ・ヴェルデを代表する、もっともよく栽培されている土着ブドウ品種だ。柑橘類やバラなどのフローラルなアロマがあるとされる。
しかし、このワインは、そこまで花のような香りは強くなく、ピンとした酸があり、若干のにがみやしぶみが特徴的だった。冷やして飲むことで特徴を表現するワインだと感じられた。
3本目もつづけてしまおう。
S. Caetanoというブランドのアリント。アリントもまた、ヴィーニョ・ヴェルデ地域の全域で育てられているブドウ品種。ただ、酸が強いため、酸を加える目的で、ブレンドに使用されるのが一般的だという。しかし、このS. Caetanoのアリントは、ブドウの熟度をあげることで、酸味をおさえ、むしろ、コクのある味わいを実現している。フレッシュなブドウの香りがあり、口あたりはまろやか。にがみが感じられるのだけれど、それをきっかけにして、さまざまな食事と合わせていけそうだ。
こんな風に、一般的な品種でも、単一で使用し、そこから、一般化したイメージとはちがう特徴を引き出すのが、昨今のヴィーニョ・ヴェルデのスタイルのひとつのようだ。
そもそもヴィーニョ・ヴェルデ地域は、小規模なブドウ栽培農家がおおく、多品種栽培は現実的ではない。農家はブドウをワイナリーに渡して醸造してもらう、というのが基本。そういう農家のなかから、自分たちのブドウで、よりよいワインを造ろうと、自ら醸造をおこない、あるいは栽培に手間暇をよりかける農家がでてきたり、異業種からワイン造りに転身する人や、資本を投ずる人がでてきている。こうしてヴィーニョ・ヴェルデはいま、変化している。そして、まだまだかなりリーズナブルな価格とはいえ、高級化もしているのだ。
4本目のAB Valley Winesという、若いワイナリーが造るOpcao Avesso 2017を飲んだときなどは、あれ?とおもった。これ、ホントにヴィーニョ・ヴェルデ?
なにせボトルをかしてもらって見てみればアルコール度数は13%もある。発泡はしておらず、果実由来の甘みと酵母に由来するのだろうか、香ばしさがある。アヴェッソという品種は、ヴィーニョ・ヴェルデ地域の南部、山で栽培される品種。オレンジやピーチ、アーモンド、フローラルさがまざったアロマがある、とされている。別府さんによれば、「いま波にのっている品種」だそうだ。「力強く男性的な品種。塩っぽい旨味、熟成するとナッツのような味わいも感じさせる」との評価。
このワインのように、ヴィーニョ・ヴェルデも高級化するとガスを添加しない。もともと、リンゴ酸が多く、瓶内でマロラクティック発酵がおきてガスができていたのが、ヴィーニョ・ヴェルデの発泡の原点。しかしワイン造りをつきつめていけば、熟成という発想もうまれる。そのときに、ガスはあえて添加するようなものではなくなってくる。
つづいては、料理(鮎の塩焼き)との兼ね合いもあって、ロゼが挟まる。Ageda Ponte da Barcoという生産者のEstreia Rose 2017。ヴィーニョ・ヴェルデを代表する黒ブドウ、ヴィニャオンを中心に、ボラサールという赤ワイン用品種に、ロゼ用のエスパデイロという品種が加わる。ヴィニャオンはヴィーニョ・ヴェルデの白以外のブドウ品種のなかでは代表的な、最大の生産量の品種だ。果皮の下まで色のついたブドウである。こういうブドウからできるワインは、ワインの濃厚さ以上に色が濃くて、タンニンがあって、酸っぱくてしぶい、みたいな印象があるけれど……
このロゼは香りはイチゴをおもわせる甘さがあって、味わいは酸味が爽やか。ちょっとトマトのような印象も抱いた。トマトっぽい味を料理に付け加えたいときに、これを飲むという手はどうだろう。日本ではカツミ商会が輸入していて、参考小売価格は1,200円というから、ロゼ好きの筆者としては発見だった。
どう発音するのか、いまいちわからないままに(エストレイア ロゼと読むそうです)赤丸をしておいて、次に移る。今度はおそらく、カルトワインの類だろう。Arrochela & Camizaoという生産者のSem igual 2015。とても小規模だそうだ。ノキアで働いていた人物が造ったワインだということで、異業種からの参入である。先だって登場したアリントと、アザルという、ヴィーニョ・ヴェルデ地域の地理的な中心地点から、東にいった、山間部で育てられる品種とのブレンド。軽やかではあるけど、深みのある白ワインだ。2015年から寝かされていることによるのだろうか、熟成したワインならではのまろやかさと香りがある。アルコール度数は13.5%もある。
おもわず筆者ここで、「なんだか、いい白ワイン、という印象ですね。ヴィーニョ・ヴェルデじゃないみたい」とつぶやいてしまった。すると別府さん、いったん、頷いてから「では、ヴィーニョ・ヴェルデでなければ、どこの白ワインに似ていますか?」と、問う。なるほど、うかつなことを言ったものだ。山のワインっぽい。じゃあイタリア?ドイツ? いや、ちがう。Sem igual(イコールではない)だ。等号で結べるようなワインは、筆者の経験上はおもいあたらない。だから別府さんは「こういうワインを造る生産者は、これがヴィーニョ・ヴェルデだというのです」。
とはいえ、4本目のOpcao Avesso 2017を飲んだところから、ここまで、筆者はなんとなく日本ワインのことをおもっていた。どこか、似ているように感じる。そもそも今回の食事は和食だけれど、純然たる和食に限らず、フライとかオムライスとかハヤシライスとか、ちらし寿司みたいなものもいいかもしれない、日本の普通の食事に、こういうヴィーニョ・ヴェルデはなんとも相性がよさそうだ。
ポルトガル。海の幸にめぐまれ、欧州にインスパイアされた日本の食の源流ではないか。ワインにおいても、先輩として、ヴィーニョ・ヴェルデは道を示してはいやしまいか?
そしてスターに
そんなことをおもっていたら、ポルトガルのブドウ界のスターがやってきた。アルバリーニョだ。
ワインはProvamという生産者のContradicao Alvarinho 2014。なんと4年も前のヴィンテージである。
本当はContradiçãoと綴る。英語でいえばContradiction、日本語でいえば矛盾という意味だ
スペインと国境を接するヴィーニョ・ヴェルデ地域の一番北の内陸、モンサン・イ・メルガッソで栽培する、一番高級な品種。それがアルバリーニョ。アルバリーニョはほかの地域でも栽培されているけれど、モンサン・イ・メルガッソのアルバリーニョじゃないと、ヴィーニョ・ヴェルデとアルバリーニョと、ダブルでブランドを表記できないそうだ。ブレンドしたら、ヴィーニョ・ヴェルデとは名乗れるけれど、アルバリーニョとは大書できない。ほかの地域で育ったアルバリーニョだとIGミーニョという原産地呼称になるという。
それは今後、変わっていくかも知れないけれど、アルバリーニョはそれだけ、特別扱いなのだ。たとえば、ヴィーニョ・ヴェルデの大きな輸出先であるアメリカなどでは、ワインは、品種名でもってオーダーする。「シャルドネをグラスで」とか「カベルネ・ソーヴィニヨンを一本いれようか」とか、そんな感じで。そんなところでも、アルバリーニョは「今日はアルバリーニョで」なのである。
アルバリーニョは、カリンとかピーチ、パッションフルーツのような爽やかさ、ライチやバナナのようなエキゾチックさ、オレンジの花やスミレのような清楚な香り、ナッツのような香ばしさを表現できる。複雑で、アルコール度数も高いワインが造れる。樽をきかせたり、シュール・リーもおもしろくなる。Contradicao Alvarinho 2014では、スキンコンタクトをしているという。7ヶ月、古樽で熟成。それゆえか、オレンジワインというほどには濃厚ではないけれど、樽や果皮からくるのだろう、濃厚で複雑、大げさにいえば、ちょっとウイスキーのような熟成感がある。料理ででてきたミソの味と合うのは、発酵した味わいとの相性がいいのだろう。これはこれまででも一番、「いいワイン」感がある。日本の食事のメインディッシュに合う。
山形の平田牧場のブランド豚、金華豚の西京焼き
実をいえば、あまりアルコールに強いほうではなく、量を飲まない筆者は、ヴィーニョ・ヴェルデが自分のライフスタイルにはあんまり合わないように感じていた。軽いから、ビールの代わり、といわれても、ビールを飲むならずっとビールを飲んでいたい。ワインを飲むならワインで通したいし、だったらある程度しっかりしたワインも飲みたい。アペリティフか、と考えると、ヴィーニョ・ヴェルデの軽快さはアペリティフよりもさらに前、みたいなイメージがあった。強いて言えば、今日はずっとヴィーニョ・ヴェルデでいく、ときめて、願わくば昼間から、ヴィーニョ・ヴェルデを飲み続けるのはいいなぁ、とはおもっていたのだけれど、なかなかそんな贅沢なシチュエーションは、しばしばはやってこない。
しかし、今回で、イメージできた。日本の、かしこまらない、日常的な食の場面に、今回のような、しっかりしたヴィーニョ・ヴェルデを置いておけばいいのだ。できれば、ひとりじゃなくて、気のおけない誰かと一緒にシェアして、白とロゼを一本ずつくらいはあけたい。価格は高くない。ラベルだって洒落ている。
なんだかそれって、とても、おしゃれじゃないか? そういえば、友達のハンサムな歯科医がヴィーニョ・ヴェルデのファンだった。彼は普段もヴィーニョ・ヴェルデ、友達をあつめてのホームパーティーでは、ちょっと特別なヴィーニョ・ヴェルデをあけるといっていた。そういうことか!