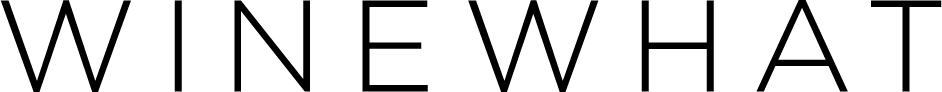クヴェヴリ
ジョージアのワインは木の樽やタンクではなく、地中に埋めた粘土の壺で熟成させる。その壺が「クヴェヴリ」と呼ばれる。大きさは容量100リッターくらいから最大で3,000リッター、一般的には600~1,800リッターと言われている。紐状の粘土を回転台のうえで回しながら作っていく。
クヴェヴリを作れる職人はジョージア国内でも数人。40~60日乾燥させたあと、10~12日かけて焼き、焼き上がったら80度に温め、その内側に熱した蜜ろうを塗り、外側に石灰と川砂を混ぜたものを塗って出来上がり。それを地中に埋める。右は、クヴェヴリを開けて試飲する様子。
クヴェヴリは、「マラニ」と呼ばれる石造りの蔵の床に埋め込まれる。そのマラニを作っているところ。
「赤」「白」「ロゼ」に続く、新たな選択
「オレンジワイン」という言葉を聞いたことがあるだろうか。
「オレンジワイン」といっても、オレンジを使うわけではない。ブドウから造られる、れっきとしたワインで、文字通りオレンジ色をしていることからその名がついた(枯れた色合いから、「アンバーワイン」という人もいる)。
ではなぜ、オレンジ色なのか? ロゼワインとはどこが違うのだろう?
まずは、ワイン造りの基本をおさらいしてみよう。白ワインは、白ブドウの果皮と種子を取り除き、クリアな果汁のみを醸造して造る。
一方、赤ワインは黒ブドウをまるごと使い、果皮の色素を抽出して造る。
ロゼワインの場合は、果皮と一緒に発酵させる、ブドウを潰して果汁に色を移すなど、いくつか方法があるが、基本的に「黒ブドウ品種を、白ワインのように造る」ケースが多い。
では、「オレンジワイン」はどうやって造るのか。
ひと言でいうと、「白ブドウ品種を使い、赤ワインのように造ったワイン」だ。ロゼワインと色は似ているが、アプローチは正反対なのだ。
「オレンジワイン」は、ブドウをまるごと潰して造るため、ブドウの果皮や種に含まれるポリフェノールやタンニンなどの成分がワインにほのかな色合いを与え、複雑な香りや味わいを醸し出す。だから、白ワインのように飲みやすく、赤ワインのような厚みや深みを併せ持ち、テクスチャーのしっかりとした味わい深いワインとなる。
果皮と共に漬け込む「スキンコンタクト」を行う生産者も多いが、「オレンジワイン」の漬け込み時間は白ワインの比ではない。そして、漬け込む時間の長短で、味わいの幅が大きく広がるところも面白い。
白ワインの酸味が苦手な人、赤ワインの渋みが苦手な人にこそ、試してほしいワインでもある。
メモ ワインの定義
赤ワイン
黒ブドウを使って造られるワイン。見た目が赤い。ブドウ果汁だけではなく、果皮や種子、場合によっては果梗を一緒に発酵させる。果皮に由来する赤い色がつくほか、果皮や種子に多く含まれるタンニンが、
渋味や苦味をもたらす。
白ワイン
主に白ブドウを使って造られる。タンニンが含まれる果皮や種子を取り除き、ブドウの果汁のみを発酵させるため、透明に近い色や黄緑色、薄い黄色、黄金色などになる。
ロゼワイン
ピンク色のワイン。赤ワインと同様、果皮や種子、果梗を浸漬させて発酵を開始し、着色した時点で分離する「マセレーション法」、赤ワインを造る過程で、上層の色の薄い果汁を取り出す「セニエ法」、黒ブドウと白ブドウの果汁を混合して発酵させる「混醸法」、黒ブドウの果皮の色素を果汁を絞る際に得る「直接圧搾法」がある。
赤ワインと白ワインを混ぜるのはほとんどの場合で禁止されているが、例外的に許される場合もあり、シャンパーニュのロゼの一部は、その方法から造られる。
オレンジワイン
明確な定義はなく、白ブドウを使って造るため、分類上は白ワイン。ただし、赤ワインのように、果皮や種子、果梗を果汁に長時間接触させることで、赤ワイン同様、タンニンがあり、果皮等に由来する色が着く。その色からオレンジ(アンバー)ワインと呼ばれる。使用する品種によっては、むしろピンク色に近い色になる場合もある。
世界最古の伝統製法が、世界の新潮流に
「オレンジワイン」は今、ワイン消費世界一を誇るアメリカのトレンドをリードするニューヨークをはじめ、ソムリエや専門家の間で、静かなブームとなっている。
だが、「オレンジワイン」の造りそのものは、紀元前6000年から続く「ワイン造りのルーツ」ともいえる伝統的製法だ。
その起源は、黒海沿岸に位置し、「ワイン発祥の地」とされるジョージア(旧グルジア)にあった。
ジョージアでは、8000年も前から、土に埋めた「クヴェヴリ」という素焼きの土器にぶどうを入れて潰し、皮や種を一緒に発酵させてワインを造っていた。今でもこの造りは受け継がれており、2013年にはユネスコの無形文化遺産として登録されている。
「ヴァンナチュール」との違いは世界でワインの醸造技術が向上するにつれ、培養酵母やステンレススチールタンクが多用され、よりフレッシュでクリーンなワイン造りが主流になった。
一方で、原点に回帰し、自然なワイン造りを追求する生産者も増えている。ブドウの持つ味わいを最大限に引き出したワイン造り、いわゆる「ヴァンナチュール」だ。
「オレンジワイン」も、果皮や種を含めたブドウそのものの味わいを引き出す造りという点では「ヴァンナチュール」と共通するが、「ヴァンナチュール」が思想的なものであるのに対し、「オレンジワイン」はあくまでも製法のひとつであることは覚えておきたい。
とはいえ、色だけでなく、その造りの裏にあるワイン造りの歴史や、造り手の思いをこそ味わってほしい。

クヴェヴリを開ける作業は子どもに教えながら一緒に行うこともある。伝統継承でもある。
オレンジワイン復活の立役者
イタリア北東部にあるフリウリ・ヴェネツィア・ジュリア地方や、それに続くスロベニアでも、200年以上前から白ブドウ品種を醸して造る「オレンジワイン」が造られていたという。
90年代には、同地の「ラディコン」が、白ブドウ品種のリボッラ・ジャッラで、果皮を長期間漬け込む伝統製法を復活させた。
ラディコンは、世界に「オレンジワイン」のカテゴリーを確立させた立役者でもある。
ちなみに、フランスのジュラ地方には「ヴァンジョーヌ」=「黄色いワイン」があり、ポルトガルには「ヴィーニョヴェルデ」=「緑のワイン」がある。
赤・白・ロゼだけじゃない。ワインの世界は本当にカラフルだ。