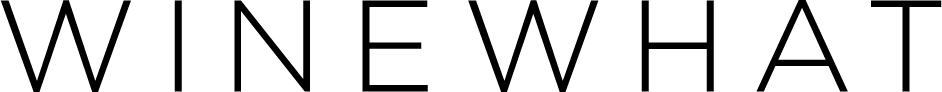1867年、パリ北東ラ・ヴィレット
ごく単純にいえば、今日の牛肉の安定供給を支えているのは「屠場」や「屠畜場」と呼ばれる食肉加工施設である。いくら大量の牛を育てても、それを肉に変える施設がなければ始まらない。例えば東京都港区にある日本最大の屠場「芝浦と場」は、2017年1月に6119頭の生きた牛を食肉に加工している。稼働日1日あたり実に360頭のペースで日本の牛肉食を支えているのだ。
そのような一大工場としての牛の屠場が世界で最初に操業を開始したのは1867年、パリ北東のラ・ヴィレットでのことであった。
ナポレオン三世のもとで帝都改造計画を推し進めていたセーヌ県知事ジョルジュ・オースマンが、それまで町のあちこちに散らばっていた小さな屠場を廃止し、それらの諸機能を郊外へ移して一元化したのだ。これは当時200万人に上ったというパリジャンの胃袋を満たす世界最新・最大の屠場となった。

1840 年ごろのイギリスの肉屋の模型。François Salvetti, Rue des bouchers:Les métiers de la viande à travers les âges, Editions Hermé, 1986, pp. 84-85.
このとき屠畜機能のみを郊外へ移設できたのは、町なかまで肉を腐らせずに運ぶ冷蔵保存技術が完成したからでもある。
このころ登場した蒸気機関も牛や食肉の流通を加速する。こうして町なかから牛が姿を消し、人の目につくところでは屠畜は行われなくなる。
結果としての「おいしそうな」肉だけが町の肉屋の店先に並ぶようになった。
さて、パリに近代屠場が誕生した直後、今度はアメリカの交通網の要、シカゴにさらに進んだ大規模屠場が建てられた。全米各地からシカゴに連れてこられた夥しい数の肉用牛は、まずユニオン・ストックヤードと呼ばれる広大な飼養場に留め置かれる。そこで大量のトウモロコシを与えられ短期間で太らされた後、屠場へとうながされる。
1892 年に撮られたシカゴの屠場の写真(ただし写真の上から絵を描いて修正している)。Peter Bacon Hales, Silver Cities: Photographing American Urbanization, 1839-1939, p.206.
こうして牛たちは次々と天井に這わせたレールに逆さまに吊られ流されていく。そのあいだに従業員らの分担作業によって血を抜かれ、皮を剥かれ、内臓をはずされ、胴を二つに割られ、枝肉にされる。ここでシカゴ屠場がパリにもまして本格的に導入したこの「高架レール方式」が、今日にいたる食肉の「効率と速度」による大量生産体制を整えたといえよう。
その後、二度の世界大戦に勝利したアメリカでは順調に中産階級が育ち、彼らは1950年代にもなれば、今度は牛肉の大量消費生活を享受し始める。安価な端肉でできた、子供でも手軽に食べられるファストフード、ハンバーガーが普及するのもこのころだ。
そしてそのようなアメリカ発祥の食生活モデルが世界中に広がっていく。