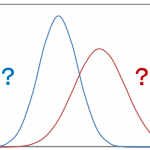そもそも『イタリア土着品種研究会』って?
先日、wine-whatで取り上げられていて、私もやや気になっておりました。
日本人のイタリアNo.1ソムリエの林 基就氏が会長をつとめる「ヴィーノハヤシ」がスタートしたワイン研究会です。
イタリアって全ての州で盛んにワインが作られている上に、その土着品種を徹底研究する会って・・・。なんてマニアック・・・。
と思いきや、実は、土着品種からイタリアの食の魅力、そして食を愉しむライフスタイルの提案が目的のワクワクの会でした。名前こそ「土着品種研究会」という、エジプト考古学研究会的な匂いが漂いますが、実際行ってみると全然そんな感じはありません。
ちなみに、私はネグロアマーロもそんなに飲んだことのないレベルですから。安心してこの記事を読んでくださいませ(笑)。ネグロアマーロというものを飲んだことがないのに、土着品種研究会に勇み足で参加しに行ったのですから(笑)。
ネグロアマーロって何?
この品種のワインたち計19本をブラインドにしてみんなで試飲したのですが、ネグロアマーロはどうだとかの蘊蓄の前に、改めてワインの愉しさを感じました。
そもそもワインって、もっと人生や食を愉しむためのものですからね! 開き直りました。
一言で言うとですね、実家のおばあちゃんの部屋、実家を感じる親しみのあるオーラがあるんです。果実の凝縮感は共通してて、甘さが残るのがこの品種の特徴のようです。でも甘ったるいとかではなく、綺麗にまとめて整っている感じがあります。
同じ品種ですが、飲む度にいろいろな角度の、違う食欲が湧いてきて、これ何に合うかなとか考えたくなるんですよね。
それがワインってモノの魔力ですね。
林さんもおっしゃっていたのですが、典型的なスタイルというものの捉え方には、マーケティング的にそうなった背景もあるから一様には言えないと話されていました。
その中で地産地消、その地に根付いている郷土料理があり、その料理と寄り添い続けてきたワインというものがある。今、ワイナリーたちはいろいろな試行錯誤していている。つまり明確な方向性が決まっている訳ではないと。
世界が繋がっている中で変化し続ける価値、でも変わらない価値もあるからスタイルが生まれてくることもある。そんなことをおっしゃっていた気がしました。
ワインに限らず、これからそういう時代ですね。結局、いろいろなスタイルがあるから違いを楽しめるし、知っているから凝り固まることもない。
この品種研究会はいわばワインを通じた食全体を考え、これからの人生を愉しくしていくためのライフスタイル研究会です。そう思って酔っぱらいながら帰ってきました。
さて、本日のマイベストたちですが、私がA~Sまで試飲させていただいて大好きだったのはこのワインたちです。特に一番左のTAGAROさんの作るSeicaselle Negroamaro(2015)は、華やかな結婚式にぴったり。
*仕込みとかそういうのではありません。
その中でも、私の一番、金メダルはこれです。
このワインだけでお肉はいらない、いや、お肉はいる! ソースはいらないんじゃないかと思うくらい濃厚で、でも飽きない精緻なまとまりがある赤ワインです。
なんか超いいことあった時とかテンション上げたい時にバッチリ。「愉しくなってきた〜〜!」まるで口の中が鼓舞されているようです。
ジャンフランコ・フィノさんの ”jo” Negramaro Salento 2014(ヨ ネグロアマーロ サレント2014)
覚え方も「研究」してみましたので、発表します・・・。「美味しいネグロアマーロヨッ!」(笑)
値段調べたらお肉が買えなくなるくらいの高めなお値段でしたが(笑)今度特別な日にお肉とセットで飲んで見たいと思いますヨ!
イタリア土着品種研究会の詳細も、皆さん、いい大人ですので、自分で検索して調べてくださいヨ!
おしまい。