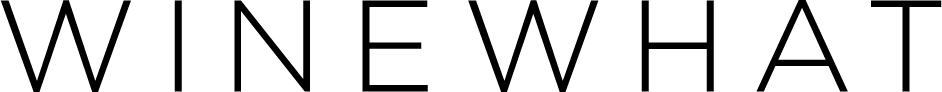百合草梨紗
静岡県出身。21歳でボルドーへ留学を決意。留学中、年間200軒以上の格付けシャトーを訪問。2002年、ボルドー商工会議所が運営する専門学校にて、商経済、ワインの醸造及びテイスティングを学び、優秀な成績で卒業。その試飲能力の高さから、ボルドー、パリを筆頭とするワインの有力メダルコンクールの審査員を務めた。2006年、ボルドーにて、日本人最年少ネゴシアン(ワイン商)として、マチュ・クレスマンとカイワイン設立。グランクリュを含む多くボルドーの生産者と取引をしており、信頼も厚く、扱い量も多い。2015年から、世界一の美味しいワインを造るべくワインメイカーになった。
シンデレラストーリー?
百合草梨紗さんは明るい。コロコロ笑って元気いっぱい。
「すごいですね、って人に言われて、はじめて、あっ、そうみえるのかって気づくくらいなんです」
そしてワインに夢中だ。サンテミリオンの街の中心部から東に11㎞ほど、サンフィリップテグイという村にある、1.65haのメルローの畑を、百合草さんと、夫のマチュ・クレスマンさんが買ったのは2015年の11月。2016年の10月10日にそこでブドウを収穫し、約2年を経て、2018年の7月31日に初のボトリングをした。ワインの名はシャトージンコ。ジンコはフランス語で銀杏を指す。3,600本ほどが造られ、日本向けにリリースされたばかり。そのタイミングからちょっと遅れての11月に百合草さんは来日した。
「18年の収穫は9月27日に終わって、そこから醸造で3週間くらい。一区切りついたので、日本に来ました。8歳の長女と2歳半の次女はいま、マチュが面倒をみてくれています」
マチュさんは150年ほどの伝統あるネゴシアンの一家の出身だ。
「そんな家ですから、日本人の私は最初は気後れもしていたんですが、娘が生まれて変わりましたね」
ワインとの出会いは、友人のワインの先生と複数回参加したワインの試飲会。そこで語られ
る話が、最初はわからず、やがて理解できるようになり、ついには独自の感想を抱くようになる、という経験をして、ワインにハマった。
そして、好きなワインがサンテミリオンのものだったので、では、と21歳の頃サンテミリオンへと赴いてしまった。
「最初は4カ月間の、遊学ですよね。朝、語学学校にいって、午後はシャトーでワインに触れる日々でした。その次の年に、ボルドー商工会議所が運営している専門学校で、ワインを流通や商取引のことも含めて学びました。マチュに出会ったのもそこです」
本場の専門学校でカリキュラムをこなすことでも、おそらく若い日本人にとっては、簡単なことではないはずで、さらに、百合草さんは、ワインの判断において傑出したものがあったそうなのだけれど、本人は、そういう自慢話みたいなことはまるっきりいわず
「そのあとインターンでマチュはアメリカに行って、私は日本に帰りました。ボルドーに戻ったのは2006年。当時アメリカでインポーターしていたマチュと、マチュはアメリカ、私は日本と、マーケットの担当をわけてカイワインと
いうワイン会社をつくったんです。それから大体10年が経ったころ、美容院の雑誌で、ドメーヌ・ルロワの記事を読んで、ぼそっと、私もこんなふうにやってみたいな、とつぶやいたら、マチュが、じゃあやってみる?って。それから
畑を探して、ルシン家が丁寧に手入れしていた畑が買えることになって……」
条件のいい畑を見つけるのは苦労した、という。しかし、話だけ聞いていると苦労は共感しづらいものだから、百合草さんの経歴をシンデレラストーリーみたいに受け止める人がいるのもわからなくもない。それで最初の発言になる。
「言われて、そうかって気づくんです。自分はワインの聖地、ボルドーでワインを造っている。もっと可能性がある、頑張らないと。ワインが造りたくてボルドーに行ったわけではないけれど、出会いと縁に助けられて、教わって、いまボルドーで自分が飲みたいワインを造れている」
「ワインって人をつなぐとおもうんです」という言葉が、百合草さんのこれまでをまとめているようにおもう。
自慢のプリンセス
ワイン業界との付き合いが深いマチュ&梨紗夫妻。ボルドー以外の選択肢はなかったんですか?とたずねてみると
「あったのかもしれません。でも、そうならなかった。いま考えれば、ボルドーのワインが好きで、ワインの世界にはいったのに、ボルドー以外でワインを造るというのは、人生として変ですよね」
明確な目標設定をもって、そこに至ろうと悩み努力する、というのはもちろんあるのだろうけれど、百合草さんはおそらく、強い芯のようなものがって、出会いや肌感覚から、ブレることなく自分の行く道を選べるのだろう。その芯の強さは、百合草さんのワインからも感じるのだ。
「もちろん、ワイナリーでルモンタージュやピジャージュ、樽熟成など、仕事はします。でもワインは、私が造っているのではなくブドウが造っているとおもっています。樹の世話は大変で、冬場の剪定なんて寒くて辛くて。でも、一本一本でちがう樹が愛おしくて、そのブドウが造るワインを、私はプリンセス・ジンコと呼んでいます。3人目の娘なんです」
オーク樽は新樽で500 リットルの大樽が主。石灰質の土壌由来のタンニンとの相性が良いだろうと導入したところ、その効果は想像以上だったという。プレスしたワインは1 年樽で熟成している
子どもを、王子・姫と呼ぶのはフランスの普通の愛情表現ではあるけれど、シャトージンコのワインは力強くて、むしろ男性的とも評されそうな味わい。でも、お母さんには、ジンコ姫。芯のしっかりした、スケールの大きそうな娘さんだ。
「まだ若くって。飲む一日前にあけるのがいいかもしれません」
オーガニックでやっているのも、認証がほしいからではなく、家族の週末の家でもあるワイナリーの目の前の畑だから、なるべく化学的なものは使いたくない、という愛情の発露。娘たちが口のまわりを紫にして食べるブドウは、皮が厚く、食感はサクサクして、味は濃厚。周囲の畑とくらべても、自慢の果実だ。
ワイナリー目の前の畑。標高100 メートルと高く、土壌は1.5 メートルほどの表土が粘土質。その下に石灰の層がある。風通しがよく、水はけもよい。品種はメルロー100%で平均樹齢35 年。2017 年に購入した、0.15ha の樹齢80 年の古樹の畑もある。また、白のメルローであるメルロー・ブランも少量栽培していて、隠し味的に2017 年からアッサンブラージュしている
「いろいろなワインの造り方のいいとこ取りをして、自分が飲みたいシャトージンコのワインを造らないと、ここでやっている意味がないし、ここでやっているのだから、この場所の味を出したい」
テロワールの表現と、百合草さんのエゴは相反しない。一本一本味がちょっとちがう、というような不安定なワインでもない。土地もブドウも、百合草さん同様、芯が強いのかもしれない。すべてがピタッとはまっている感じだ。
とはいえ、百合草さんの我を通しきったワイン。自信はあっても売れてくれるかどうかは心配なようで
「はじめたものだから伝統にしたい。これから、叩かれることもあるかもしれないけれど、出過
ぎた杭は打てない、ともいうみたいだから」
「頑張らないと」と繰り返す。そんな責任感も、お母さんだ。
銀杏のように
広島に原爆に耐えた銀杏の樹がある。銀杏は強い樹だ。シャトージンコの銀杏もまた生命力のシンボル。シャトーには下の娘さんの誕生のときに植えた銀杏の樹があるという。
「私はボルドーで死ぬ」
伝統の最初の一歩を踏み出した。やがてジンコの木は古樹になり、シャトーのメルローの樹齢も越えるだろう。銀杏に見守られ、その頃、ワインを造っているのはふたりの娘さんかもしれない。