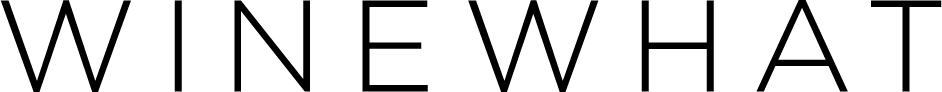ホテル雅叙園東京の広間にて。
キアンティには7つのサブゾーンがある
キアンティに7つのサブゾーンがあることをご存じでしょうか? 冒頭、宮嶋氏からキアンティワインに関する概略が語られた。
1963年にイタリアで「D.O.C.法(原産地呼称管理法)」が成立すると、それ以前から知られていたキアンティは当然のように1967年にD.O.C.となり、1984年に「保護原産地呼称ワイン」であるD.O.C.G.に昇格する。
キアンティの範囲は広い。
もともとは、現在「キアンティ・クラシコ」を名乗っている地区のワインのことだったけれど、ちょうどムッソリーニが支配していたファシズムの時代に、宮嶋氏曰く、「ぐーっと産地を広げちゃった」からだ。イタリアは第一次大戦で戦勝国にはなったものの、経済は低迷していた。これをなんとかすべく、輸出を増やす方策として、「キアンティが成功しているんだったら、もっと売らない手はない」と考えられのだ。
国家ファシスト党を率いるベニート・ムッソリーニが独裁体制を築いたのが1925年。フィレンツェ県、シエナ県、アレッツォ県、ピストリア県のブドウ栽培業者が集まってキアンティ・ワイン協会を設立したのは1927年である。D.O.C.法ができる40年ほども前だ。
「逆に言えば、これだけ広い範囲に広がって、いまだにキアンティというワインは1億1000万本も世界中で売れて、愛されている。ということは、トスカーナというところがそれほどのポテンシャルを持つ産地だったということですね」と宮嶋氏は明るく続けた。
7つのサブゾーンを示す図。
トスカーナの場合、ひとつの地理的特徴がある、宮嶋氏は指摘する。
それは、地中海ににゅっと飛び出た細長い長靴型のイタリア半島は、ちょうど真ん中をアペニン山脈が背骨のように貫いている。それゆえティレニア海側もアドリア海側も、海と1000m級の山との距離が短いところが多い。そういうイタリアにあって、トスカーナはアペニン山脈が東にズレていて、山から海までの距離が長い。しかも、その間に丘陵がいくつも広がっている。
それゆえ、「トスカーナは山のキャラと海のキャラの間にいくつもの半音階というか、多様なニュアンスが混在している。だから銘醸地として好まれている」。
キアンティの生産地域で7つのサブゾーンがつくれるのも、アペニン山脈から海まで、テロワールの複雑さと多様性があるからなのだ。
キアンティは、ピサを除けば、基本的に内陸部で、アルノ川が削った渓谷があり、沖積土壌がある。内陸部はどちらかというとコンチネンタルな気候で、酸が生き生きしてエレガントなワインが生まれる。海岸部は地中海性気候で、どちらかというと果実が芳醇でグラマーな、カリフォルニア的なワインが生まれる。
キアンティ・ワインは1万5,500ヘクタールのブドウ畑から80万ヘクトリットルつくられている。ボトルにすると、およそ1億1000万本。キアンティ・クラシコが7000ヘクタールなので、その倍近い。プロセッコの5億本には及ばないにしても、非常に高い生産量を誇っている。
キアンティはサンジョベーゼ70%以上、30%までは他の品種を補填できるが、白ブドウは10%以下、カベルネ品種は15%以下と定められている。
キアンティにはいくつかの決まりごとがある。ブドウはサンジョベーゼが70%以上。白ブドウは10%まで、カベルネやメルローのように自己主張の強いブドウは15%までとされている。
キアンティには「ダンナータ(vino d’annata)」と呼ばれる早飲みのテーブルワインもあり、「これはこれで、すごく魅了的」と宮嶋氏はいう。
「あまり考えないで、リラックスしたい時もある。そういうときに普通のキアンティをちょっと冷やして飲むと、口のなかがさっぱりして、スパイシーで、魚にも合う。誤解されているけれど、早飲み用のワインは白を入れるのもアリ」
それから宮嶋氏は隣のキアンティ・ワイン協会のアルヴェス氏に話を振った。
キアンティの万華鏡
アルヴェス氏がイタリア語で歌うように話したことを、宮嶋氏が次のように訳した。
「キアンティについて話すのは簡単です。ただ、キアンティにはいろんなレベルがあります。
サンジョベーゼのいろんな表情がキアンティに含まれている。今日は、その下部地区(サブゾーン)を揃えて、それぞれのテロワールの特徴を見てもらうというのが趣旨で、できるだけその地域の特徴を出してくれるようなワインを選んだ。キアンティには『万華鏡』のように様々な表現がある。セミナーのタイトルも、『キアンティの万華鏡』だというんで、変えさせたんですけど、私(笑)」
「キアンティの万華鏡」ではわかりにくい、と宮嶋氏は考えたらしい。アルヴェス氏が続けたことばを宮嶋氏が次のように訳した。
「サンジョベーゼにも、伝統的なつくり方と近代的なつくり方があるし、さらに醸造の要素もある。どこまでがテロワールの要素で、どこまでが人間の要素なのか、ワインを飲んだときにそれを考えてマイナスして残ったモノを見ないと本当のテロワールはなかなか見えてこない。全部のワインに共通しているのは、キアンティ・スタイルというか、非常に飲みやすいワインであるということです。生産者の名前を隠したのは、みんなに好奇心を持ってもらいたいから。造り手は誰なのかなと思って飲んで欲しい、と思って」
さらにアルヴェス氏はこう付け加えた(と宮嶋氏)。
「試飲というのは個人的なものなので、みなさんの主観を犯すようなことはしたくない。ただ、私は生産者のスタイルについては、ちょっと話したい。
もちろん、グラスのなかのワインというのはその土地のテロワールの産物です。
なかでもサンジョベーゼはどこに植えられるかによって非常にキャラが変わる。ピノ・ノワールとかネッビオーロと一緒で、テロワールを素直に表しちゃう品種です。そういう意味では洗練されたワインとも言えるし、通ゴコロをくすぐるというか、これはどこのテロワールかなと考えちゃったりする品種でもある。
キアンティというひとつの呼称だけれど、7つの地区を飲んでいただくことによって、7つの地区を旅した気分になってもらいたい」

左から、時計の逆回りに1→7番。
キアンティ・コッリーネ・ピザーネは潮っぽい
いよいよ、7つのサブゾーンのリゼルヴァ 2015の試飲となった。リゼルヴァは、通常のキアンティの熟成期間が4カ月なのに対して、24カ月と定められている。
1番目は、ティレニア海にほど近いピサの南西のエリア、キアンティ・コッリーネ・ピザーネの、キアンティ地区でも増えている有機栽培のワイナリーによるワイン。前述の理由により、ワイナリー名は伏せられている。
「非常に太陽を感じさせるワイン」と
ルカ・アルヴェス氏(が語ったイタリア語の宮嶋氏による訳)。
「みずみずしくてジューシーで、タンニンがきついというよりは、若いキアンティを想像させる、飲みやすさがある。典型的ではないキアンティのトーンとして、地中海的なトーンがある。ローズマリーとかバルサミコとか、塩、コショー、海のニュアンス。海に近いので、砂の多い土壌で、貝殻の化石が砂の中に埋まっていて、気候は温暖で、内陸部のワインに比べると、すぐに楽しめる。こういう喜ばしい飲み口はキアンティの典型ではある」
アルヴェスのことばを通訳したあと、宮嶋氏はこう付け加えた。
「ただ、あとで出てくるアレッツォとかシエナとかに比べると、それほど厚みがあるようには思えない。これはよし悪しの問題ではなくて、果実が熟成して、なめらかなんだけど、最後に塩っぽさが残る。それはこの辺りのテロワールに塩っぽさが残っているから。そういう意味では非常に面白い。塩っぽいニュアンスがないと、もっとシンプルなワインに思える。コッリーネ・ピサーネの特徴がよく出たワインだと私は思いました」
ピサといえば、ピサの斜塔。12世紀に着工、14世紀に完成した。キアンティ・コッリーネ・ピザーネはピサの南に位置する。

ルカ・アルヴェス氏と宮嶋勲氏。7つのワインはアルヴェス氏が選んだ。
キアンティ・モンテスペルトリはクラシコに通じる
2番目はキアンティ・モンテスペルトリ。同じくアルヴェス氏の語るイタリア語を宮嶋氏が通訳しながら、ご自分の知見を加えた。それを要約すると、こんな感じになる。
7つのサブソーンのなかで一番面積が小さくて、1997年に加えられた、一番新しい地区で、フィレンツェの西20kmぐらいのところにある。
モンテスペルトリは、ワインづくりの伝統のある産地で、トスカーナのなかで一番ブドウが植えられている。
土壌は、海の底にあったので、基本的に石灰岩だけれど、この辺りは川があって粘土や石ころなどもあって、いろいろ混じり合っている。
気候は海洋性と大陸性のちょうど間ぐらいで、生産者もごちゃ混ぜで、いろんなタイプのひとがいる。
そういう意味では一言でとらえにくい産地。生産者も小さいのがいっぱいいるので、それぞれが俺のスタイルで、職人的なワインづくりをしている。ようは大きな会社がないから、生産者のスタイルが出やすいといえば出やすい。
1番と2番、どちらもサンジョベーゼ100%だけど、ニュアンスがぜんぜん違う。特にピサのあとでは、山のトーン、タンニンが厳格になっていて、サンジョベーゼらしい。1番が優しく包み込んでくれる感じだとすれば、こっちはより引き締まった感じで、「ちょっと肉でも欲しい」みたいな感じになる。サンジョベーゼならではの厳格で生き生きした感じが出ている。
キアンティ・クラシコに通じるトーン、われわれが親しんだタンニンがある。
標高150mで、それほど高くない。アメリカンオークを使っているけれど、樽香が強い感じはない。1番は大樽で、2番は小樽。タンニンが厳格なので、小樽を使っている。150mという標高の高さより、内陸的な印象のほうが強い。単一畑でもある。キアンティでも、単一畑で栽培する動きがある。

ルカ・アルヴェス氏。
キアンティ・コッリ・アレティーニは南のトーン
3番目は、アレッツォの近くのキアンティ・コッリ・アレティーニ。
「こっちのほうが産地のキャラがもっと立っていると思います」と宮嶋氏。
「これはまたぜんぜん違う。タンニンが甘くて、1番と比べると、タンニンの量が多い。口当たりは、攻撃的な、刺々しいところはないんだけど、後からタンニンが感じられる。でも非常に熟した、アルコールもちょっと強めで、力強いサンジョベーゼで、南のトーンが感じられる」
続いて、アルヴェス氏(のイタリア語を訳した宮嶋氏)。
「そうなんです。アレッツォの特徴は、南なんだけど、アペニン山脈に近い。アレッツォのなかにもいろんな地域があるけれど、これは標高500mのブドウです。ただ、これをブラインドで飲んで、標高500mだと当てられる人はいないと思う。250mぐらいだと言っちゃうと思います。標高の高さよりアレッツォの特徴のほうがよく出ている。
樹齢35年で、カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローが7.5%ずつ、合わせて15%入っている。今までのサンジョベーゼ100%とは違う。最初の3つでも、味わいと香りがずいぶん違います。共通しているのは、飲み終わった後に、『もういっぱい飲みたい』という気持ちにさせる喜ばしさがあるということ。サンジョベーゼは基本的に酸が多い品種なので、フレッシュでべたつかない。飲みやすさ、これがキアンティというものの特徴です」
イタリアワインの伝道師、宮嶋勲氏。
「私が付け加えるとすると」と断ってから宮嶋氏。
「アレッツォ地区は今まではあまり表に出ない。一番南にあるので、過小評価されている。欠点はニュアンスの多様性がない。心地よいんだけど、わりと果実の複雑さがない。チェリーとかのトーンがボーンと出て、アルコールがあってグラマーなので、このワインを飲んで最初に思いつくことは、『北のほうの弱いワインをこれで強化してあげたい』という気持ちになりますよね。
実際に、アレッツォのワインはグローバルウォーミングの前、キャンティ・クラシコの補強に無茶苦茶使われていたんですよね。だから、基本的には使っちゃいけないんだけど、そういうこと、ワインではよく行われています。
こういうことって、現地を訪問すれば、このひとが誰と友達なのか、すぐにわかりますよね。醸造家がしょっちゅう電話してきて、一緒にクルマに乗って行っていく姿を見れば、誰でもわかる話で、このワインがあそこに行っているのはすぐにわかります。
そういう意味では、グローバルウォーミングの前と今とでは、特にピエモンテとかそうですけど、いろんなことが変わりました。ひとつは、ブドウが完全に成熟するようになったので、1970〜80年代は涼しかったということと、栽培がいまほどよくなかった。昔は生産量が多かった。今の2倍も生産していれば、当然ブドウは成熟しない。酸っぱくてアルコール度数が低いワインが多かった。それを補強するのにアレッツォのワインが使われた。
当然、それをうまくつくるにはブレンドの腕がいる。イタリアは基本的に、モンタルチーノはもちろん、バローロ地区ではよく言われるけれど、単一畑の伝統はないわけで、相互補完関係にあるいろんな特徴を持ったブドウを、名人が、これをこう入れてこうやると、本当に素晴らしいワインをつくっていた。テロワール、どうのこうの、ではない。いい悪いではなくて、美味しいワインをつくろうとしたら、ブレンドした方が美味しいに決まっています。
単一畑、テロワールの発想というのは、それを犠牲にしても、そこでしか生まれない個性を表に出していきましょうという発想なんで」
いい話だなぁ、と感心しながら、4番目のワインへと移る。